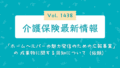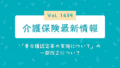会社と取引先等との良好な関係性を築く施策としてしばしば話題にあがる「利益供与」。こと障害福祉サービスにおいては、基準省令(実際には条例)により固く禁じられているところです。
お世話になったからお礼の気持ち、と安易に考えて行ったことが基準違反に…。知らなかったは通用しません。とはいえ、そもそも利益供与ってなに?そして、具体的になにが利益供与にあたるの?と疑問や不安を感じている方は少なくないはず。
そこで、今回は、障害福祉サービスの「利益供与の禁止」について基準を読み解き、基本的な考え方やシチュエーション例ごとのポイントなどをわかりやすく解説していきます。

当コラムは、障害福祉サービス事業全般に共通するものではありますが、居宅介護や重度訪問介護等の訪問系障害福祉サービス事業者向けに解説しています。
本記事は、厚生労働省令および解釈通知等を参考に作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、具体的な可否の線引きは、指定権者により異なる場合がありますのでご注意ください。本記事は、あくまで参考程度に捉えていただき、実務においては各自治体への確認等をお願いいたします。
利益供与の禁止規定の基本的な考え方
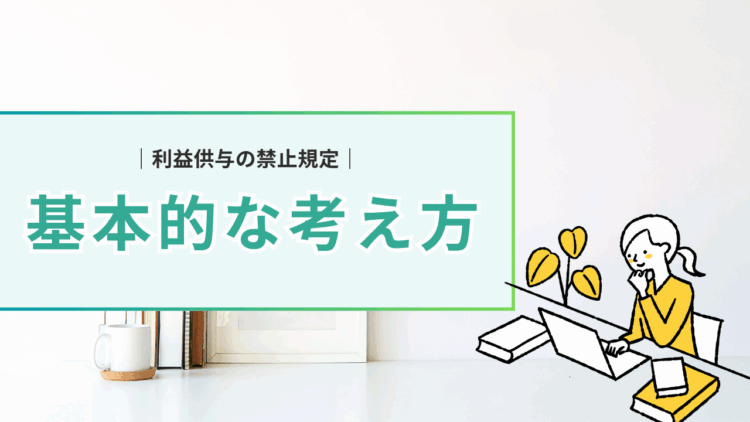
(利益供与等の禁止)
第三十八条 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。2 指定居宅介護事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」より引用
障害福祉サービスの利益供与の禁止は、基準省令第38条に定められている規定です。
第1項は、居宅介護事業者が利用者等の紹介を受けた対償として金品等を渡してはいけないこと、第2項は、居宅介護事業者が利用者等を紹介した対償として金品等を受け取ってはいけないことが規定されています。

いわゆるバックマージンやインセンティブといった紹介等に対する謝礼などは、障害福祉サービスにおいてはNGということですね。
利益供与の禁止規定の趣旨
障害福祉サービスは、障害者自らがサービスを選択して利用の可否を判断すべきものであり、障害者自身の意思決定を重要視しています。
しかし、事業者が利用者紹介の対償として金品等をもらったり、渡したりという行為をすると、サービスを利用する障害者の意向はきちんと反映されない、または汲み取られず、意思決定が歪められてしまいます。
このため、障害者の意思決定を歪める誘因行為を防ぎ、障害福祉サービス事業者等の紹介・選択が公正中立に行われるように、利益供与の禁止規定が設けられているのです。
「紹介」とはどのような行為をさすのか
基準省令の解釈通知によれば、紹介とは、「障害害福祉サービス事業者と利用者またはその家族を引き合わせること」を指します。また、次の内容等も紹介に含まれるとされています。
- 障害福祉サービス事業者に利用者等の情報を伝え、利用者等への接触の機会を与えること
- 利用者等に障害福祉サービス事業者の情報を伝え、利用者の申出に応じて、障害福祉サービス事業者と引き合わせること
金品の多寡に関わらない
たとえ1千円であろうが、1万円であろうが金銭や品物の多寡に関わらず、財産上の利益を紹介の対償として供与または収受してしまえば基準違反になります。例えば、お礼の気持ちとして商品券や金券などを渡したり、もらったりすることも含まれるものと考えておきましょう。

よく「利用者負担額を徴収しないこと」や「相談支援専門員にお歳暮などの贈答品を送ること」は、利益供与にあたりますか?と質問が寄せられているので回答しておきます。
前者については、利益供与うんぬんの前に基準省令第21条(利用者負担額等の受領)第1項に違反するため必ず徴収してください。
後者については、線引きが難しく指定権者に確認してほしいですが、実質的に紹介に対する謝礼とみなされる可能性があります。なので基本的には贈答品は渡さない・もらわないと決めておくのが良いと思います。
「障害福祉サービスの事業を行う者等」には、一般企業や個人も含まれる
これまで障害福祉サービスの事業を行う者等の「等」になにが含まれるのかは示されていませんでしたが、令和7年3月31日付けで解釈通知が改定され、障害福祉サービスの事業を行う者等には、「障害福祉サービス事業者
以外の事業者」や「個人」も含まれる旨が明記されました。
したがって、障害福祉サービス事業者ではない一般企業や個人に紹介の対償として金品等の利益を供与・収受した場合も、基準違反となります。
シチュエーション例から考えるヘルパー事業所が注意するポイント
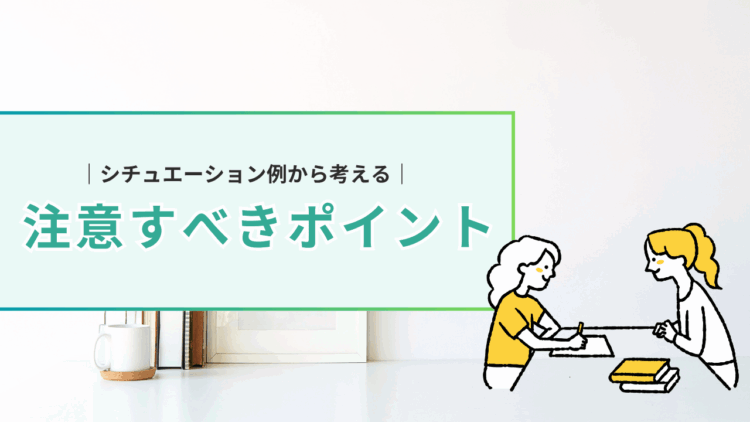
ヘルパー事業所の利用者紹介ルートは、相談支援事業所や障害者本人からの直依頼、他のヘルパー事業所・障害福祉サービス事業所、既存の利用者からの紹介などさまざまです。
いずれのルートにせよ、紹介する・受けることの対償として金品等の利益を渡す、または受け取ると基準違反になるわけですが、本項では、現場に沿った形でシチュエーション例をあげ、ヘルパー事業所が注意すべきポイントを解説していきます。
新規依頼をしてくれた相談支援事業所へ見返りを渡す
計画相談を行う特定相談支援事業所が比較的多い地域では、利用者獲得の営業先は、第一に相談支援事業所があがります。この際に「ヘルパー事業所を探している方がいれば、ぜひうちを使ってください」と依頼して紹介を受け、その見返りに謝礼を渡すなどは、基準省令第38条第1項に違反します。
セルフプランの利用者に他の障害福祉サービス事業所を探す
全国的に相談支援事業所数が足りておらず、地域によってセルフプランの利用者はまだまだ多いです。
既存利用者にセルフプランの方がいる場合は、利用者から信頼のおけるヘルパー事業所があれこれと通所先の障害福祉サービス事業所等を探したり、また、計画相談をつけようとなれば懇意にしている特定相談支援事業所を紹介したりといったこともあるでしょう。
この際に、利用者等を紹介した見返りとして謝礼を受け取ると基準省令第38条第1項に違反します。
他のヘルパー事業所に移管するまたは移管を受ける
既存利用者へのサービス提供が難しくなった場合や、自事業所のみでは対応困難な時間枠が発生した場合は、他のヘルパー事業所を探さなければなりません。
計画相談がついているなら相談支援専門員が探してくれますが、それでも基準省令第13条(サービス提供困難時の対応)により、自事業所でも他のヘルパー事業所を探して紹介する等を求められます。
このようなシチュエーションで、他のヘルパー事業所に移管する、あるいは他のヘルパー事業所から移管を受ける際に、紹介の見返りとして謝礼を渡す・受け取ると、基準省令第38条第1項または第2項に違反します。
既存の利用者からの友人の紹介を受ける
既存利用者の友人や知人がヘルパー事業所を探しているといったケースも少なくありません。
通所先等の何らかのコミュニティで出会ったのか、古くからの友人・知人なのかはさまざまですが、このようなシチュエーションで、利用者が友人を紹介した際に、紹介した利用者・紹介された友人に金品などを渡すと基準省令第38条第1項に違反します。
斡旋業者から利用者等の紹介を受ける
ヘルパー事業所が、斡旋業者から利用者等の紹介を受けるシチュエーションは、あまり考えられないと思いますが、これは利用者獲得のための広告を想定しています。
例えば、民間事業者が運営している障害福祉サービス事業所の情報掲載サイトなどに、ヘルパー事業所の情報を掲載し、報酬を支払う場合です。
解釈通知によると、この際に、広告経由で紹介された利用者個人ごとの「紹介料」を支払う場合は、基準違反になると考えられ、情報掲載サイトなどにヘルパー事業所の情報を掲載し、掲載料を支払う場合は、基準違反にならないとされています。
つまり、利用者紹介ごとのタイミングで料金が発生する成果報酬型の広告は基準違反リスクが高いが、利用者紹介の有無に関わらない定額制の掲載課金型の広告は、基準違反リスクが低いということになります。

利益供与等は、契約書上の名目などに関わらず、実質的に、利用者等の紹介の対価として財産上の利益が提供されているかで判断されるものとされています。
なので、契約書上は掲載料となっていても、実質的に成果(紹介)ごとに報酬を支払う形態であるならば、それは基準違反になってしまうと考えられます。
ヘルパー事業所に利用者獲得の広告はそもそも不要
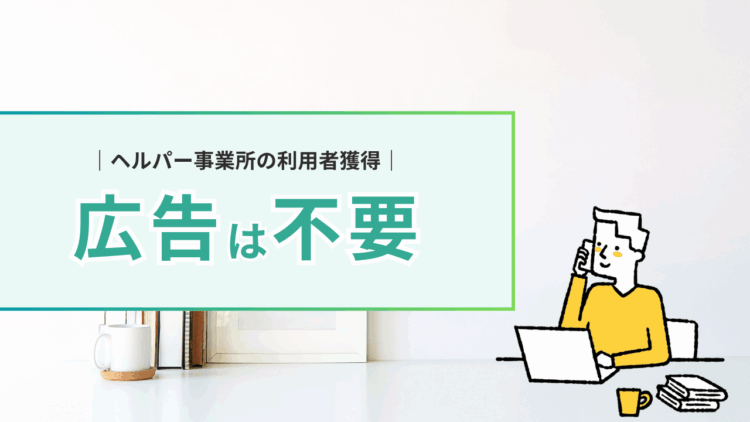
先に触れた利用者獲得のための広告は、はっきり言ってヘルパー事業所に必要ありません。
そもそも障害福祉サービス事業者は、情報公表制度により事業所情報を都道府県等に報告することでWAMNET(障害福祉サービス等情報検索サイト)に無料掲載されますし、WAMNETのみで十分です。
立ち上げたばかりの事業所からすると早急に利用者を獲得したい気持ちはわかります。ですが、相談支援事業所を主に他のヘルパー事業所などに営業を重ねていけば確実に利用者獲得はできます。

どこのヘルパー事業所も金銭的に余裕のない中で運営しているわけです。どうしても広告を出したいなら、ヘルパー会議室でみなさんの事業所を無料で紹介しても全然良いと思っていますので、気軽に相談してください。
何が言いたいかというと、たいして効果のでない広告に頼るのではなく、泥臭く必死に、地道に営業をかけまくりましょうってこと。
でも、ホームページぐらいは持っておきたい
ヘルパー会議室でホームページ制作を提供しているので、ポジショントークと思われるかもしれませんが、最低限の施策として自社ホームページぐらいは持っておきたいところです。
というのも、相談支援事業所が足りていない地域では、障害者自らヘルパー事業所に電話等で依頼してくるパターンが多くなります。この依頼までの流れは、「①障害者等が役所に出向いて支給申請を行う」⇒「②役所から事業所一覧などをもらう」⇒「③ヘルパー事業所に連絡する」という工程に紐解けますが、実は、②と③の間に「事業所名で検索する」という作業が入る場合があります。
当然ながら、依頼する事業所がどのようなところなのか、安心して利用できるところなのか、みんな不安に感じていて、それを知るための検索行動です。
こんなとき、ホームページを持っていないと、おそらくWAMNETがヒットすると思われますが、WAMNETに掲載されている情報からは事業所の雰囲気などが伝わりません。一方で、自社ホームページを持っていて、かつ検索にヒットし、それが安心を与えるホームページであれば、「この事業所に連絡してみよう」となるわけですね。
ですので、自社ホームページを作るなら、安心を与える柔らかいデザインや文言を意識し、できるかぎり事業所の外観・内観・職員の写真画像などを使うようにしましょう。

ちなみに、これは利用者獲得に限らず、ヘルパー等の採用活動においても同じことが言えます。また、検索行動の観点から、ヘルパー事業所でよく使われている名称は基本的に避けた方が良いかなと思います。