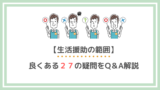訪問介護のサービスの一つ、「生活援助」は掃除や洗濯などの家事の支援をすることを指します。
訪問介護は介護保険サービスなので、何でもしてあげられるわけではなく、訪問介護における生活援助のサービスにも様々なルールが存在します。

そこで今回は
✓訪問介護における同居家族がいる場合の生活援助の取り扱い
について簡単に解説します。
利用者やご家族から相談があった際、しっかり説明できるようにしましょうね!
訪問介護サービスの生活援助は、同居家族がいても利用できる?できない?

さっそく結論から言うと、
訪問介護の生活援助サービスは同居家族がいてもサービス利用は可能です。
ただし、
適切なケアプランに基づき、必要と認められれば、サービスを利用することが可能になります。
訪問介護の生活援助についてよく言われることと言えば、「同居家族がいると、生活援助のサービスは利用できない。」だと思います。
確かに生活援助は、原則同居家族がいる場合、サービスを利用できません。
ですが、あくまで原則です。すぐに諦めてしまってはいけません。
同居家族がいても生活援助サービスを利用できる根拠理由
では、訪問介護の生活援助のサービスは、どのような場合において同居家族がいても可能になるのでしょうか?
厚生労働省では下記の通り示しています。
- 利用者の家族等が障害や疾病等の理由により家事をおこなうことが困難な場合
- その他の事情により家事が困難な場合
それぞれを具体的に解説していきます。
理由①利用者の家族が障害や疾病等により、家事を行うことが困難な場合
同居している家族が疾病や障害等よって、家事が行えない場合も生活援助のサービスを利用することが可能になります。
例えば
✓同居家族がうつ病で家事の支援が期待できない
✓同居家族が癌の治療中で家事の支援の期待ができない
などがあります。
理由②その他事情により、家事を行うことが困難な場合
その他事情の具体的な例をあげると
✓家族が高齢で身体機能が低下しているため家事が行えない
✓家族が就労しており多忙で不在の時間が多く、日常生活に支障をきたす場合
✓介護者の介護疲れがひどく共倒れの危険がある場合
などがあります。

このように、利用者に同居家族がいるという事実だけで、一概に生活援助を利用できないわけではありません。
ケアマネジャーがしっかりとアセスメントを行い、必要であれば利用できるということになります。根拠があれば利用できるということですね。
内縁の妻や夫は同居家族とみなされるのか?
内縁の妻や夫であっても同居していて生活を共にしているのあれば、同居家族とみなされ、その方の援助を優先することになります。

戸籍上の関係性が重要なのではなく、その方に介護力があるかどうかがポイントになります。
同居家族のいる利用者に、生活援助サービスを提供する際の手順
基本的には次のようなステップで進めていきます。
- 同居家族の有無を確認する
- 利用者、家族の状況をアセスメントする
- アセスメント後、本当に生活援助サービスが必要か検討する
- ケアプランを作成する
- サービス担当者会議で、生活援助の必要性を話し合う
- サービスを提供する
- ケアプランの見直し(必要性を再確認)

上記のステップはケアマネジャーが中心になって進めていくことになりますが、訪問介護のヘルパーも手順はしっかりと理解しておきましょうね!
まとめ
今回は訪問介護における同居家族がいる場合の生活援助サービスの取り扱いについて解説しました。
「同居家族がいると、生活援助のサービスは利用できない。」と思い込み、考えることをやめてしまっていたヘルパーも結構多いです。
今回の記事を読んで、同居家族がいたとしても、しっかりとした根拠があれば生活援助のサービスを提供できるということが分かっていただけたと思います。
また訪問介護の生活援助には「できること」「できないこと」の線引きが多くありヘルパーを悩ませますよね。
当サイトではリアルな現場でよくある25個をQ&A方式で解説した記事を公開しています。
良かったら下記をご活用ください!
※サービス提供責任者の仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。