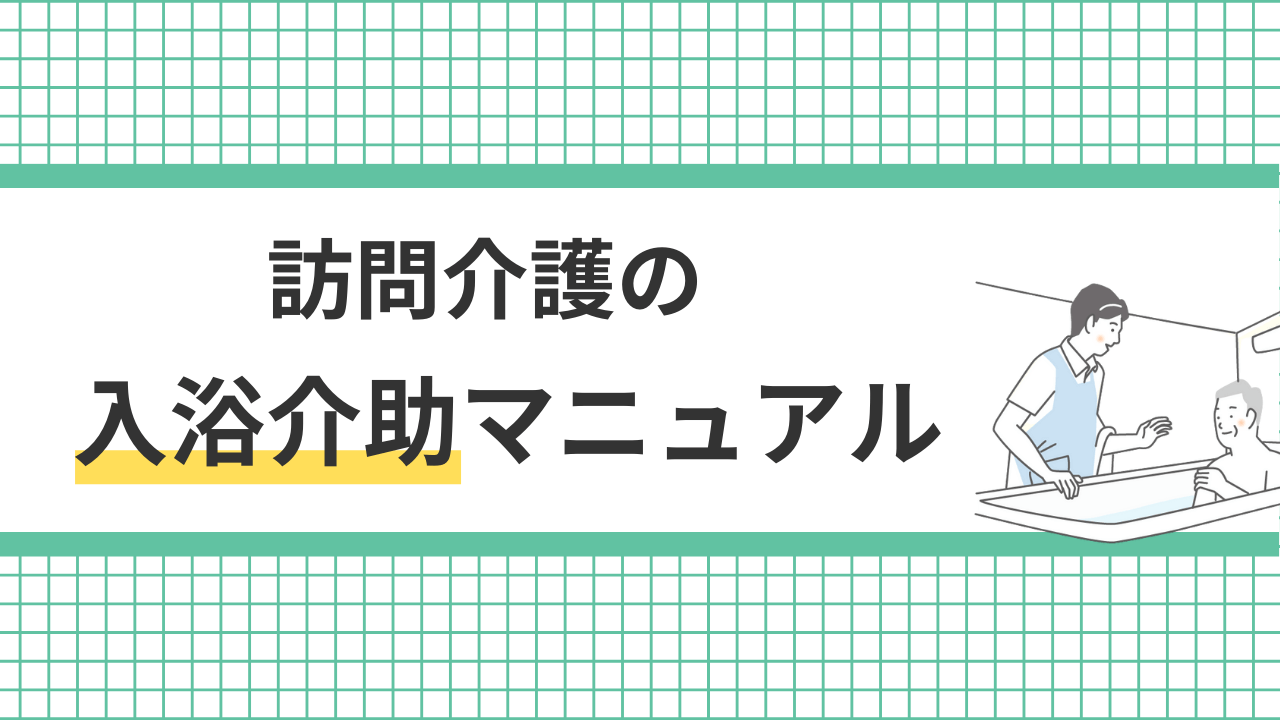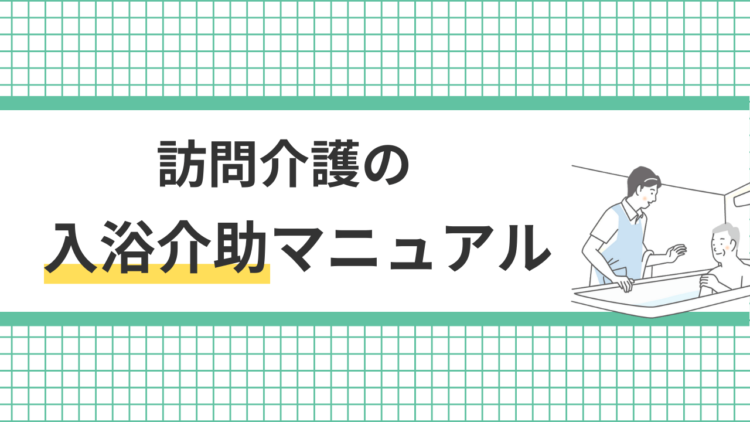

訪問介護で働きだして間もない初心者ヘルパーです。
今度、はじめて入浴介助をすることになったけど、一人でうまく介助できるか不安…
気をつける所やコツがあれば教えてほしい。
ヘルパー会議室では、こんな悩みを解決すべく訪問介護の「入浴介助マニュアル」を作成しました。
本マニュアルは、初心者ヘルパー向けに入浴介助の基礎知識や事前準備、注意点、実践手順をわかりやすく解説した入門書です。
本マニュアルを読むことで、訪問介護における入浴介助の基本をすべて理解でき、実際の現場で利用者個々の状態に合わせた介助を行う一助となります。
介護サービス情報公表により求められている入浴介助マニュアルや研修資料としても使えますので、ヘルパーに限らず管理者やサービス提供責任者の方々も参考にしてください。
訪問介護における入浴介助とは

訪問介護における入浴介助とは、病気や障害などにより一人での入浴が難しくなった利用者に対して、ヘルパーが入浴に係る見守りや介助を行うサービスです。
排せつ介助や食事介助などの身体介護と並び、多くのケースで活用されています。
入浴介助は、清潔を保つだけでなく血行を良くしたり、ストレスを軽減したりと身体・精神の両面への効果が期待でき、利用者の生活の質を高める上で欠かせません。
しかし一方で、転倒や体調の急変など事故リスクが高いサービスでもあります。
加えて、一般的な入浴介助では、移動・移乗の介助や更衣介助などの身体介護も複合的に行うため、適切な知識や技術を十分に身につけておくことを求められます。
ケースごとに入浴介助の方法は異なる
入浴という行為は、これまで利用者が自ら行ってきたごく自然な日常生活の一部です。
そのため利用者なりの入浴ルールやこだわりが必ずあります。
例えば
- 体を洗う前に一度湯船につかる
- ボディソープは使用せず石鹸を使って体を洗う
- 洗身用タオルは堅めのものを使う
- 体を洗う順番は腕から
- シャワーで体の泡を流さず、湯船のお湯を桶ですくって流す
などさまざま。
また、身体機能についても下肢筋力が低下していたり、片麻痺があったりとそれぞれ異なりますので、一律的な介助方法では、安全かつ快適な入浴を実現することはできません。
利用者によっては、下手にヘルパーから手を出されると邪魔に感じ、恐怖を覚えることもあります。
もちろん初見からいきなり最適な介助を行うのは難しいでしょう。ですが、事前にサービス提供責任者が作成した手順書をきちんと読み込んでおくことや、利用者とのコミュニケーションの中で確認しながら個々に適した介助方法を検討することが重要です。
入浴介助は、転倒などの危険が伴うがゆえに、他の身体介護と比べて高度な技術が求められるサービスと言えます。新人ヘルパーからすれば「転倒させてしまうかも」「事故を起こしてしまうかも」と感じてしまうかもしれません。
しかし、それは利用者にとっても同じで「このヘルパーに自分の身を任せても大丈夫だろうか」と心配しているものです。入浴を安全かつ快適に行ってもらうためにも、ぜひこれから紹介する介助の基本や手順をしっかり学んでおきましょう。
訪問介護における入浴介助の目的と効果
訪問介護における入浴介助には以下の目的と効果があります。
\ 入浴介助の目的効果 /
- 感染症の予防
- 社会性の保持・促進
- 血行の促進
- リラックス効果
- コミュニケーションの促進
- 健康状態の把握
清潔の保持
入浴により皮膚の清潔を保つことは細菌感染の予防につながります。
皮膚が不潔な状態だと細菌が体内に侵入しやすくなり、擦り傷や切り傷からの皮膚感染症や陰部からの尿路感染などを引き起こす要因となります。
社会性の保持・促進
定期的な入浴により身だしなみを整えることは、生活にメリハリをつけ、本人の自信につながります。
それにより他社との関係構築をスムーズにし、社会性の保持・促進に寄与するでしょう。
血行の促進
入浴中、特に温かいお湯に浸かっている時は、副交感神経が働き血行が良くなります。
それにより筋肉や関節の緊張がほぐれ、コリや痛みが軽減されたり、老廃物や疲労物質が軽減されたり、といった効果が期待できます。
訪問介護の利用者には、慢性的な痛みや冷え性、身体のこわばりなどを抱えた方々が多いです。こうした方々にとって湯船につかることは、浮力により身体を動かしやすくなるため、より身体をほぐしやすくなるでしょう。
リラックス効果
入浴は、心身をリラックスさせる効果があります。
温かいお湯につかることで、筋肉がほぐれ、ストレスや疲れが解消されます。
また「入浴のあとはよく眠れる」との声を利用者からよく聞きます。体が温まりリラックスすることで、眠りの質が向上し、睡眠の質を高める効果も期待できるでしょう。
コミュニケーションの促進
入浴中は、周囲の目や声が気にならないプライベートな空間です。
そのため普段、ほとんど会話をしない無口な利用者が、自身の経験や思い出を話し始めることがあります。時には生活に対する思いや悩みを打ち明けられることもあり、利用者を良く知る機会となるでしょう。
ただし、入浴は利用者とのコミュニケーションを深めるチャンスですが、つい話が長くなってのぼせてしまう恐れがあります。折を見て「また次に聞かせてくださいね」などと伝え、中断する配慮も行いましょう。
健康状態の把握
入浴介助の際には、普段衣服で覆われて見えない肌を露出するため、皮膚の状態や身体の動き、体調変化などの健康状態をいち早く把握できます。
また例えば、皮膚の傷や湿疹、浮腫、筋力低下などの異常があれば、早期にケアマネジャーや医療職と連携し対処することで、症状の悪化を防ぐ一助となるでしょう。
具体的な観察のポイントについては後で詳しく解説していますので、そちらを確認してください。
訪問介護における入浴介助の8つの基本原則
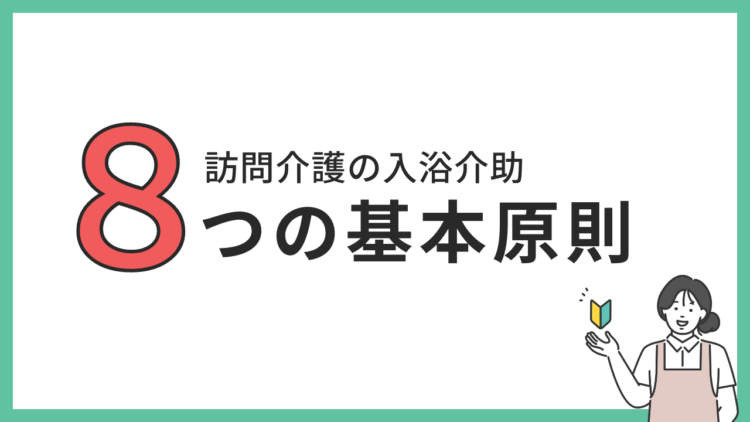
訪問介護における入浴介助は、以下、8つの基本原則をもとに行います。
\ 入浴介助8つの基本原則 /
- 声かけ
- 食事前後の入浴は避ける
- 入浴前のバイタルチェック
- 全身観察
- 安全確保
- プライバシーの配慮
- できることは自分でしてもらう
- 身体を洗い方
基本原則①「声かけ」
入浴の際は、利用者へ声をかけ、必ず同意を得てから実施します。
開始時のみならず入浴中も「お部屋は寒くありませんか」「お湯は熱くないですか」など環境に配慮する他、「今からシャワーをかけますね」「シャンプーを流すので目を閉じていてくださいね」といった、動作ごとに予告することも大切です。
それにより利用者の不安感が軽減され、ゆっくりと入浴を楽しんでもらえます。
また利用者の中には、入浴を拒否する方もいるかも知れません。拒否の原因は人それぞれですが、「気乗りしない」「着替えなどが面倒」「裸を見せたくない」などさまざま。
こうした拒否がある場合、決して無理強いをしてはいけません。
「汚れているから綺麗にしましょう」「何日も入っていないから臭くなりますよ」など、否定的な言葉は使わず、「温かいお湯に浸かると気持ちがいいですよ」「体を洗うとさっぱりしますよ」といった、ポジティブな言葉を使った声かけを心掛けましょう。
基本原則②「食事前後の入浴は避ける」
空腹時の入浴は血糖値の低下を招き、めまいや貧血を起こす可能性があります。
また食後すぐの入浴は消化不良を起こす恐れがあるため注意が必要です。
そのため基本的には、食事前後の入浴は避け、1時間以上空けたタイミングが良いでしょう。
基本原則③「入浴前のバイタルチェック」
入浴前に必ずバイタルチェックを行います。
血圧や体温、脈拍の他、表情や話し方にも気を配り、普段と変わったところがないか確認します。
入浴は、みなさんが思っている以上に体力を消耗する行為です。体調不良時に無理をして入浴すると悪化させてしまいます。
人によっては体調が芳しくない時であっても、心配させまいと振る舞う場合がありますので、食欲の有無や歩き方など、見落としそうなポイントもしっかり確認しましょう。
体調が悪いと思われる時は無理をせず入浴中止とする、もしくは清拭や足浴に切り替えて様子観察を行うなど、柔軟な対応が必要です。
体温や血圧が高い場合は、入浴の中止を検討します。しかし人によって入浴可否の上限値は異なりますので一概に決めることはできません。一般的には血圧は139/89㎜Hg、体温は37℃が入浴可否の上限値とされていますが、主治医と相談の上、事前に指示を仰いでおきましょう。
基本原則④「全身観察」
入浴介助の際は、全身状態を観察できる絶好の機会です。
以下のポイント参考に観察を行ってください。
| 皮膚の状態 | 乾燥、発赤、湿疹、傷、かゆみ、褥瘡の有無、水虫、爪の色・周囲の状態などを観察します。 |
|---|---|
| 身体の動き | 立位・座位時の姿勢の安定性、歩行の状態、関節の可動域、筋力、筋肉の緊張度などを観察します。 |
| 骨格の状態 | 骨の変形の有無などを観察します。また骨折が疑われる場合は、動かせない部位の痛みや腫れなどを観察しましょう。 |
| 浮腫の有無 | 浮腫は、血液やリンパ液が組織にたまり、むくんで腫れる状態です。特に足首や手首、顔、目の下などに現れやすく、心臓や腎臓、血管疾患などの病気に罹患している利用者の場合は十分に観察してください。 |
※以下ヘルパー会議室のコラムでヘルパーの観察力を高める方法を解説しています。こちらも合わせてチェックしてみてください。
参考:【訪問介護の観察マニュアル】基本観察項目と気づく力を高める4の法則
基本原則⑤「安全確保」
入浴介助時の事故は、軽介助や見守りレベルの利用者であっても起こります。
介助にあたるヘルパーは、起こりうる事故をあらかじめ想定し、安全確保に努めましょう。
以下に想定される事故リスクとその回避策をまとめました。
| 転倒 | 浴室や脱衣所の床は濡れているため滑りやすく、転倒しやすい場所です。
自立度が高くとも一瞬の油断がもとで転倒に至るケースも少なくありません。床に泡が残っていないか確認したり、転倒防止のマットを敷いたりなどの対策を講じましょう。 また、居室から浴室までの導線を確保することも重要です。つまづきそうな物を置かないようにし、通路の安全を確認してください。 |
|---|---|
| ヒートショック | 急激な温度差によって血圧が上下すると、脳梗塞や心筋梗塞、めまいや立ちくらみが起こります。
特に冬場は暖かい居室から移動してきて裸になるため、浴室・脱衣所と浴室外の温度差があまりないようにする必要があります。 入浴介助の前段階で、ヒーターなどを活用して室温を調整しましょう。また浴室の床がタイルの場合は、冷たいため少し前から温かいシャワーを出しておくなどの方法も有効です。 |
| 火傷 | シャワーの湯温が高く火傷に繋がるケースがあります。
やけどはヘルパー側の適切な準備で防止できる事故ですので、必ず温度確認を行いましょう。 |
| 溺れる | 下肢筋力が弱っている利用者の場合、浴槽内で足を滑らせてお湯の中に潜り込んでしまう危険があります。
浴槽内で座位をとれるよう必要に応じて介助したり、浴槽内に滑り止めマットを敷いたりなどの対策を講じましょう。 |
| のぼせ | お湯の温度が高すぎたり、長時間お湯につかり過ぎたりするとのぼせやすくなります。
特に高齢者の場合、心臓への負担も大きいため、湯温は38℃から40℃程度、湯量は浴槽の半分程度、湯につかる時間は5分程度に留めるよう調整しましょう。 |
| 脱水 | 気持ち良いからと長湯になると、汗をかき脱水を引き起こす危険性があります。
入浴前後にコップ1杯の水を飲む、浴槽に浸かる時間を短くするなどで予防しましょう。 |
基本原則⑥「プライバシーの配慮」
入浴介助では、人前でデリケートゾーンをさらすという最も私的な領域に立ち入ります。
「裸を見られたくない」「恥ずかしい」、このような感情を抱くのは人として当然のことです。認知症などの疾患や障害の有無にかかわらず、利用者のプライバシーには細心の注意を払らわなければなりません。
例えば、
- 陰部等のデリケートゾーンにタオルをかける
- 身体を観察する際にじろじろ見ず、サラッと確認する程度に留める
- 移動時に利用者を急かさない
などの配慮を行いましょう。
たとえ利用者と良好な関係性を築けていても、ヘルパーの一挙手一投足が自尊心を傷つけてしまう場合があります。十分にプライバシーに配慮し介助にあたってください。
基本原則⑦「できることは自分でしてもらう」
介護保険の基本理念はあくまでも「自立支援」。自分でできることは積極的に行ってもらうよう促します。
個々のADLはそれぞれですが、自立度が高い方の場合、介助者はほぼ見守りで入浴可能なケースが多々あります。
介助しなければという気持ちが先行して本来自力で行える動作を先回りすると、利用者への支援を妨げる結果になりかねません。
安全面への配慮をしながらも、利用者の能力を活かして入浴できるよう支援しましょう。
参考:訪問介護の「自立支援」実践ガイド【考え方と展開方法を4ステップで解説】
基本原則⑧「身体の洗い方」
訪問介護の入浴介助は
お湯を足元からかける→洗髪→すすぐ→洗身→すすぐ
の順に洗っていくのが基本です。
具体的な洗い方については以下のポイントを参考にしてください。
| お湯は足元からかける | 洗髪・洗身の前にまずお湯をかけます。この際には最も心臓から遠い足先からかけるようにしてください。これは利用者の身体的な負担を軽減するためですので、必ず末端→中心の順にお湯をかけていきます。 また洗髪・洗身の前にお湯をかけ温めることで毛穴が開き、汚れを落としやすくなります。 |
|---|---|
| 洗身は末端から | 身体を洗う際には、上半身なら手から、下半身なら足先から洗っていきます。これも利用者の身体的な負担を軽減するためにですが、利用者なりのこだわりや仕方がある場合はそちらを優先してください。 |
| 強くこすらない | 高齢者の皮膚は、非常に弱くデリケート。少しの刺激でも皮膚がめくれたりアザができたりと繊細です。強くこすり過ぎず「痛くないですか?」などと利用者に聞きもって、力加減を調整しながら丁寧に進めましょう。 |
| すすぎ洗いは入念に | 汚れをきれいに落とすための秘訣は、すすぎ洗いにあります。もちろん洗髪・洗身を丁寧に行うことも大切ですが、それよりも泡が残らないよう入念に洗い流すことが重要です。
また体に泡が残っていると介助時に滑る恐れがあるため、事故防止のためにもしっかりとすすぎ洗いを行いましょう。 |
| 汚れが溜まりやすい箇所は入念に | 以下の汚れが溜まりやすい箇所は、特に入念に洗いましょう。
|
訪問介護における入浴介助の必要物品
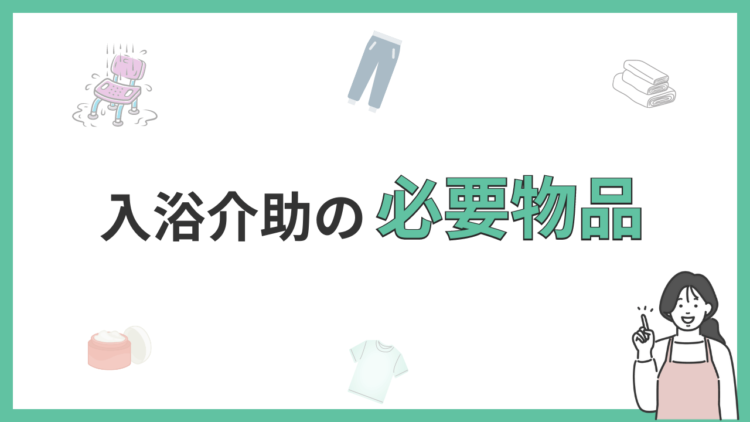
入浴介助を実施する前にバスタオルや着替え類などの物品を準備します。
以下は、訪問介護の入浴介助において一般的な必要物品です。
| バスタオル | 大きく吸水性の高いものがおすすめ。 拭く時間を短縮し着替えができるため、湯冷め防止に。 |
|---|---|
| ボディタオル | 高齢者には柔らかい素材が良い。敏感肌の人は素手で洗うケースもあり。 |
| ボディソープ | 乾燥肌の方は保湿性の高いものが良い。必要に応じて洗顔料も準備。 |
| シャンプー | 必要に応じてコンディショナーも準備。 |
| シャワーチェア(必要時) | 座位保持、立位に不安がある方の場合の入浴補助用具。 |
| 滑り止めマット(必要時) | 必要時に浴槽内、浴室⇔脱衣所の入り口へ設置。 |
| バスボード(必要時) | 浴槽へのまたぎ動作が難しい方の場合の入浴補助用具。 |
| 浴槽用手すり(必要時) | 浴槽へのまたぎ動作が可能だが不安のある方の場合に使用する入浴補助用具。 |
| 浴槽内イス(必要時) | 浴槽が深すぎる場合に使用する入浴補助用具。 |
| 着替え | 上下衣服、肌着、靴下などを準備。 |
| オムツ類 | オムツやリハビリパンツ、パッド類を準備。 |
| 爪切り(必要時) | 入浴後は爪が軟らかくなり切りやすいため、必要に応じて爪切りを準備。 |
| ディスポーザブル手袋 | 感染対策や突発的な便の処理、処方軟膏を塗布する際などに使用。 |
| 処方軟膏や保湿クリーム(必要時) | 医師から処方をうけた軟膏、保湿クリームなどを必要に応じて準備。 |
| 入浴用エプロン(必要時) | 軽介助や見守りレベルの入浴介助時に使用。 |
| 浴室用の靴(必要時) | ヘルパー側の転倒防止のため必要に応じて準備。素足で行う場合もあります。 |
| 脱衣所に設置するイス(必要時) | 脱衣所に利用者が座るイスがなければ準備。 |
| ヒーターなどの暖房器具(必要時) | 冬場に脱衣所を温めるために使用。 |
訪問介護における入浴介助の実践手順
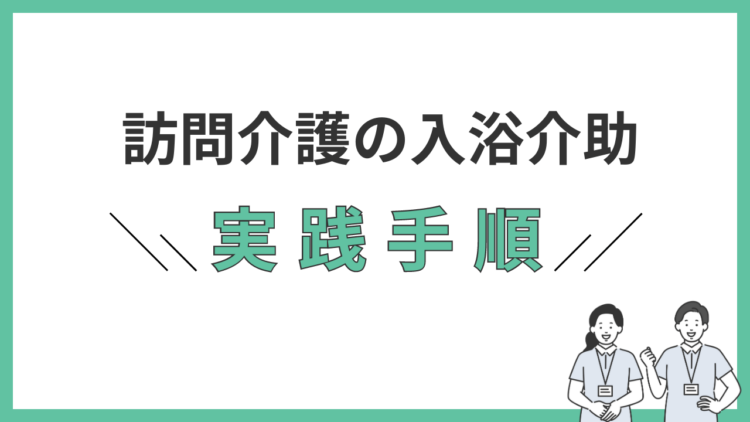
ここからは一般的な入浴介助を「入浴前」「入浴中」「入浴後」に分けて全19のstepで実践的な手順を解説していきます。
※あくまで例ですので、実際の現場では利用者個々に合わせた方法で実施してください。
入浴前の手順
- STEP1入浴の説明
入浴前に「これからお風呂に入りましょうか」などと声をかけ、入浴の同意を得ます。
拒否がある場合は、決して無理強いにならないよう、ポジティブな声かけを意識し誘導しましょう。
- STEP2バイタルチェック、体調確認
- STEP3環境整備、準備
- 浴槽へお湯をはる(38℃~40℃程度)
- シャワーチェアやその他の入浴補助用具を所定の位置へセットする
- 替えの衣類やオムツ類などを脱衣所に準備する
- 処方軟膏や保湿クリームがあれば脱衣所に準備する
- 居室から脱衣所、脱衣所から浴室への導線を確保する
- 脱衣所にイスを設置する(立位を想定し、手すり付近へセット)
- ヒーターなどで脱衣所や浴室の室温を調整する(浴室はシャワーを流しておくなど)
上記の環境整備、準備を行います。
補足として脱衣所の温度は『少し蒸し暑い』と感じるくらいがヒートショックの予防に効果的です。また脱水予防のため、この時点でコップ一杯程度の水分補給も行うと良いでしょう。
- STEP4脱衣所へ移動
利用者を居室から脱衣所へ誘導します。転倒に注意し、必要に応じて移動介助を行います。
なお、入浴の前にトイレを済ませておくとゆったりと過ごせるので、必ずトイレの希望を聞いておきましょう。
- STEP5脱衣
脱衣所に到着したら、イスに腰かけてもらい脱衣を促します。
長年の習慣から、右腕から脱ぐ人、左腕から脱ぐ人、頭から脱ぐ人、ズボンから脱ぐ人などさまざまですが、半身まひがある人に関しては、『脱健着患』の原則で脱いでいただいたほうがスムーズです。
参考:更衣介助マニュアル
- STEP6浴室へ移動
浴室に手すりがある場合は、手すりを掴んでもらい浴室へ移動します。
ヘルパーは、必要に応じて脇の下か肘を支え移動を介助しましょう。
シャワーチェアに座る際は、座面や背もたれ、ひじ掛けにお湯をかけ、しっかり温めてから座ってもらいます。
入浴中の手順
- STEP7かけ湯
座ったら利用者にお湯をかける旨を説明し、湯温に注意して足先からかけます。
必ず「熱くないですか?」と声をかけながら行いましょう。
- STEP8洗髪
目を閉じ、手で耳をふさいでもらった上で、まず予洗いします。
手が動きにくいなどの理由で耳を自身でふさげない場合は、シャンプーハットを使い、目や耳にお湯が入らないよう対策しましょう。
予洗いが終わったらシャンプーを泡立て、指の腹で頭皮全体をマッサージするように丁寧に洗っていきます。
その後、シャンプーが残らないようすすぎ洗いを念入りに行います。
- STEP9洗身(顔)
洗顔料を泡立て、可能であれば利用者に自ら顔を洗ってもらいましょう。
難しい場合はヘルパーが行います。目や鼻、口に洗顔料が入らないように注意しながら、優しく洗います。
小鼻の辺りは脂が溜まりやすく特に汚れやすいため丁寧に。その後、泡がぬるつきが残らないよう洗い流し、タオルで水気を拭き取ります。
- STEP10洗身(上半身)
上半身は指先から始まり、前腕、上腕と上っていき、肩回り、背部、胸部、腹部へと洗っていきます。利用者が自分で洗える場合は好みの順序で良いでしょう。
体型にもよりますが、乳房の下側、脇、下腹部の二面接触部分は汚れが溜まりやすい箇所です。ただれや発赤が見られるケースが多いので、洗身時も状態観察をしっかり行いましょう。
- STEP11洗身(下半身)
下半身も上半身と同じく末端(指先)から始まり、足首、ひざ、大腿部、臀部、陰部、肛門と洗っていきます。
指の間、膝裏、陰部は汚れが溜まりやすいので入念に洗いましょう。ふくよかな人の場合、鼠径部も汗をかき汚れやすいため注意が必要です。
- STEP12洗身(陰部)
陰部はデリケートな部分ですので、基本、可能であれば利用者に洗ってもらいます。
- 男性の場合の手順
陰茎→陰のう→肛門の順に洗う - 女性の場合の手順
前から後ろへ恥骨から肛門へ向けて洗う
女性の場合は、大陰唇・小陰唇に汚れが溜まりやすく、男性の場合は、陰茎のシワや包皮の内側に汚れが溜まりやすいため丁寧に洗いましょう。
- 男性の場合の手順
- STEP13浴槽へつかる
洗髪洗身が終わったら、必要に応じて手すりやバスボードなどの入浴補助用具を活用し、浴槽内へ入ります。
この際、またぎ動作時に転倒が発生しやすいため、決して急かさず本人のペースで動いてもらいましょう。
浴槽の湯量は、肩まで浸かると心臓に負担がかかってしまうため、心臓の下になる程度、3~5分を目途につかるようにします。
肩まで浸かりたい利用者の場合は、タオルを肩にかけて、洗面器で肩に湯をかけるようにすると体が温まります。
- STEP14浴槽から出る
手すりやバスボードなどの入浴補助用具を活用し、ゆっくり浴槽から出てもらいます。
その後、出口付近で軽く水気を拭き取ります。
入浴後の手順
- STEP15脱衣所へ移動
滑りやすくなっているため転倒に注意し、脱衣所へ誘導します。ヘルパーは、必要に応じて脇の下か肘を支え移動を介助しましょう。
脱衣所の椅子に座り、バスタオルでしっかり拭き取ります。
- STEP16着衣
事前に用意しておいた衣類、オムツ類に着替えます。入浴後は、入浴前に比べてバランスを崩しやすいため転倒に注意し、必要に応じて介助しましょう。
また医師から処方されている軟膏がある場合は、この時点でディスポーザブル手袋を着用し塗布します。(保湿クリームも同様)
- STEP17居室へ移動
動線に注意しながら、居室へ移動します。入浴後の疲労から足の上りなどが悪いことがあるため、段差があるところでは、特に注意を促しましょう。
- STEP18水分補給、体調確認
- STEP19後片付け
脱衣所、浴室内の物品や着替えた衣類などを片付け、必要に応じて風呂の掃除や換気を行います。
後片付けを終えたらサービス提供記録を記入し、入浴介助完了です。
さいごに
今回は、訪問介護の入浴介助マニュアルを紹介しました。
本マニュアルから入浴介助の基礎を理解し、実際の現場で活かしてください。
ヘルパー会議室では、初心者ヘルパー・サービス提供責任者向けに業務マニュアルを無料公開しています。
この機会に合わせてチェックしておきましょう。