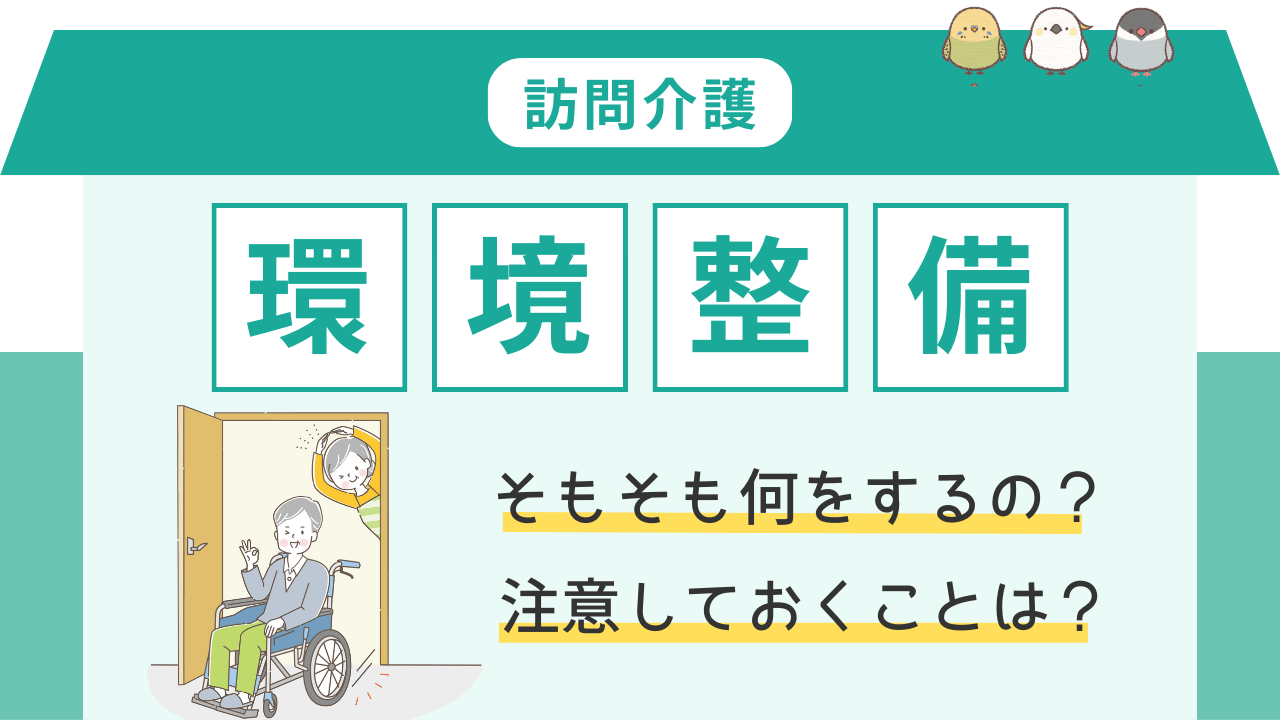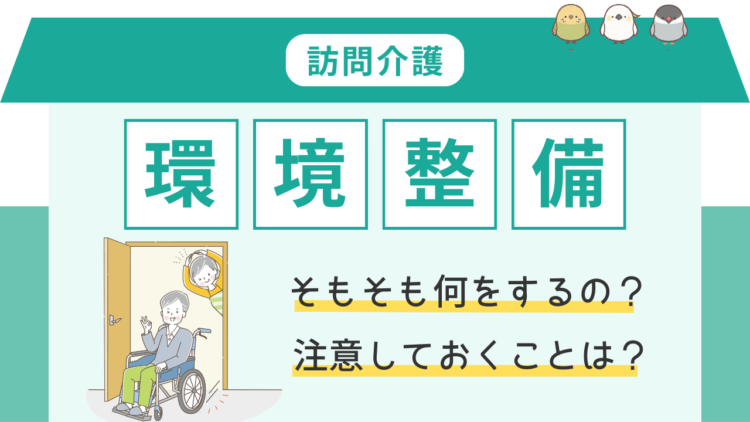

訪問介護で働き始めて間もない初心者ヘルパーです。
「環境整備」って言葉を良く聞きますが、そもそも環境整備ってなに?
具体的になにをすれば良いのか教えてほしい。
今回は、こんな疑問にお答えします。
一般的に介護業界における環境整備とは、利用者に快適な暮らしを送ってもらうために住宅環境や生活環境を整えることを意味します。
当然ながら訪問介護においてもとても大切な支援のひとつです。
しかし一口に環境整備といっても多岐に渡り、その内容をきちんと理解できているヘルパーは少ないと言えます。
そこで本記事では、訪問介護の環境整備とはなにかを解き明かし、ヘルパーが行う環境整備の内容をわかりやすく説明します。
訪問介護の環境整備とは
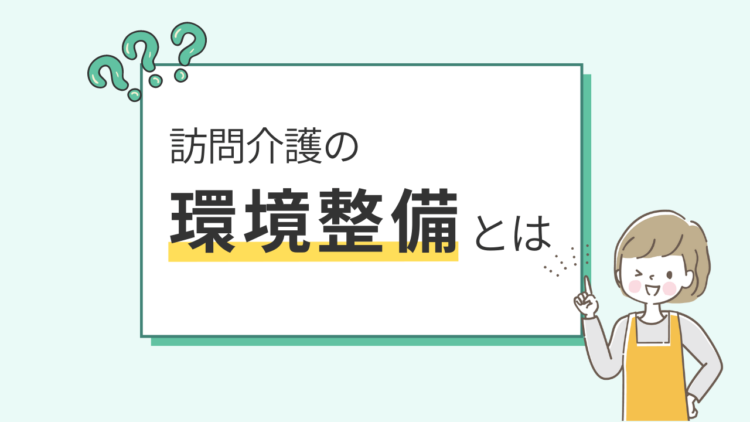
訪問介護の環境整備とは、換気、室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓等を指します。
訪問介護におけるケアの流れや手順を示した厚労省通知「老計第10号」によれば、これから行う支援の「事前準備」として位置づけられており、排せつ・食事・入浴介助などの身体介護や掃除・調理などの生活援助に付随して実施するサービスとなります。
参考:老計第10号とは?最新内容、注意点をわかりやすく完全解説
換気
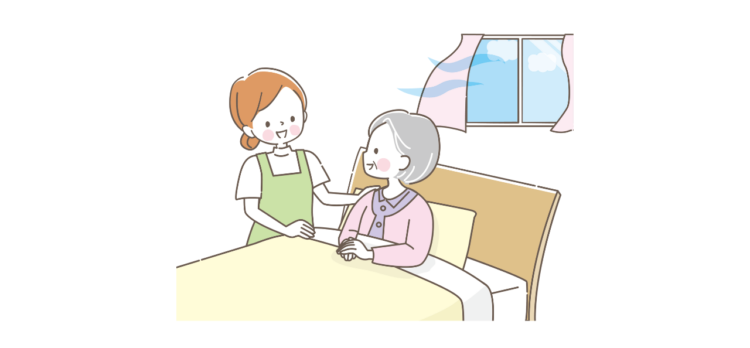
換気とは、利用者宅の居室等の窓をあけ空気を入れ替えること。
例えば掃除をする前や排せつ介助の後などに適宜行い、空気を入れ替えることでハウスダストやウィルス、悪臭等の除去、除湿、精神面のリフレッシュなどを図ります。
また、利用者の中には閉じこもりがちな方が少なくありません。
こうした外出頻度が少ない方々にとって換気は、外の空気に直接触れ、季節の移ろいを肌で感じられる貴重な機会にもなります。
室温の調整
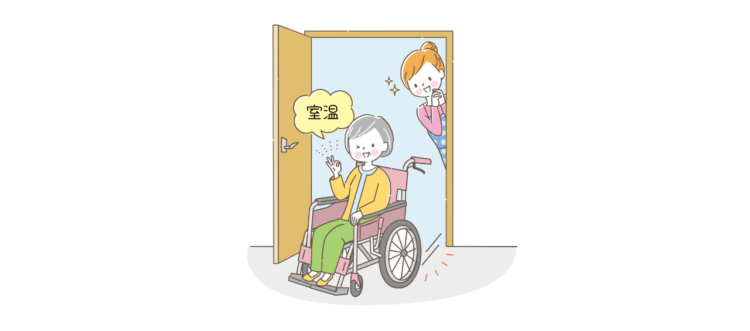
高齢である利用者のお宅の室温調整はとても大切です。
歳を取るにつれて人間の体内の水分量は減少し、温度の変化を感じにくくなります。
「夏場にエアコンをつけず厚着の洋服をきて過ごし、熱中症になる」といったケースは珍しくなく、ヘルパーは適切な温度管理にも気を配らなければなりません。
一般的に室温は25℃~28℃、外気との温度差は7℃以内が良いとされています。
また冬場は、居室とそのほかの部屋との温度差に注意しておきましょう。
洗面所や浴室、脱衣所、トイレなどは居室に比べて室温がかなり下がります。そのためヒートショックの危険が高く、温度差がある部屋へ誘導する際には、あらかじめ暖房器具で温めておくなど、温度差が少なくなるよう対応してください。

ヒートショックとは、温かい部屋から寒い部屋へ移動した際など、急激な温度変化によって血圧の急上昇や急下降、脈拍の変動などが起こる健康障害を指します。利用者の命に関わりますので十分な注意が必要です。
日あたりの調整

高齢者の多くは睡眠のリズムが崩れがち。
適度に日の光をあびることで、睡眠の質やリズムを調整するのに役立ちます。
体内時計がリセットされて昼夜の区別がはっきりとし、夜間の質の良い睡眠を促進する助けになります。
特に昼夜が逆転してしまっている利用者などには、日中の活動量だけでなく、日あたりの加減にも気を配ってサービス提供にあたりましょう。
ベッドまわりの整頓

転倒の多くは、カーペットの端のめくれや床に散らばった衣類やゴミ、雑誌、電気コードなどにつまづいたり、引っかかったりして発生します。
ですので、ベッドまわりにこれらの障害物がないかを確認し、介助に入る前に整理整頓を行いましょう。
またヘルパーは、サービス時だけでなくサービス後、利用者が1人のときの生活にも目を向けることが重要です。
サービス時に使った物品をもとの位置に戻しておくなどの基本的はもちろんのこと、ヘルパーが帰った後、利用者が安全に移動できるかどうかの視点をもって、導線の確認・確保をかならず行ってください。
訪問介護の環境整備における注意点
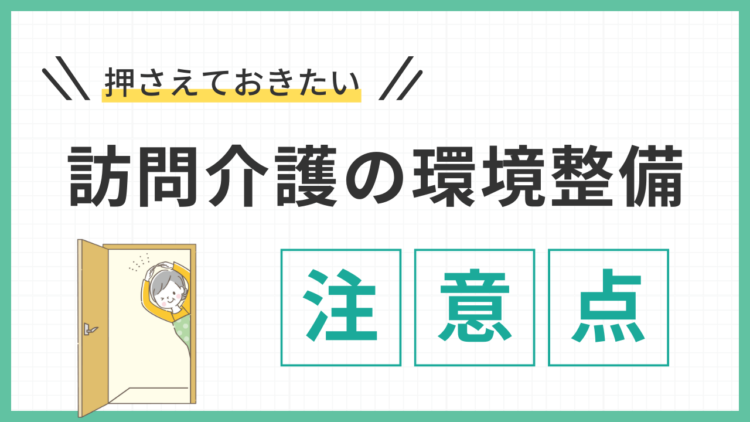
これまで訪問介護の環境整備について概要を解説してきましたが、ただ単に換気や室温・日あたりの調整、ベッドまわりの簡単な整頓等を利用者に応じて行えば良いというわけではありません。
環境整備の実施にあたって、ヘルパーのみなさんに注意しておいてほしいことが2つあります。
声かけを忘れない
注意点の1つ目は、声かけを忘れないことです。
訪問介護は、あくまで利用者宅にお邪魔させてもらう立場にあることを忘れていはいけません。
窓を開けて換気をする際や、物品に触れる際には利用者へ声をかけ、同意を得てから行いましょう。
声かけを怠って勝手に行うと、利用者からの苦情につながることもありますので注意が必要です。
自立支援の観点を取り入れる
注意点の2つ目は、環境整備に自立支援の観点を取り入れることです。
自立支援とは利用者自らできることを減らさず、可能であれば増やしていけるよう支援すること。
ヘルパーには、その利用者の現有能力をきちんと見極め、どのように支援すればできることを増やしていけるのかを常に考え実践することを求められます。
環境整備は、身体介護や生活援助に付随して行うサービスではありますが、この事前準備の段階においても自立支援を取り入れてみましょう。
例えば、ベッドまわりの整頓であれば、たとえ自立歩行が難しい方であっても「手の届く範囲をヘルパーと一緒に片付ける」などはできるはずです。
また例えば、室温調整の一環として、エアコンのリモコン操作がわからない方に「ヘルパーが操作方法をレクチャーして利用者自ら使えるように支援していく」のも良いでしょう。
さいごに
今回は訪問介護の環境整備について解説しました。
訪問介護の環境整備は、その他の職種と比べてより利用者の生活に密接した視点から行うものだと言えます。
ぜひヘルパー初心者の方は本記事を参考に、日々の業務に活かしてください。
当サイト「ヘルパー会議室」では、ホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。
この機会にあわせてチェックしておきましょう。