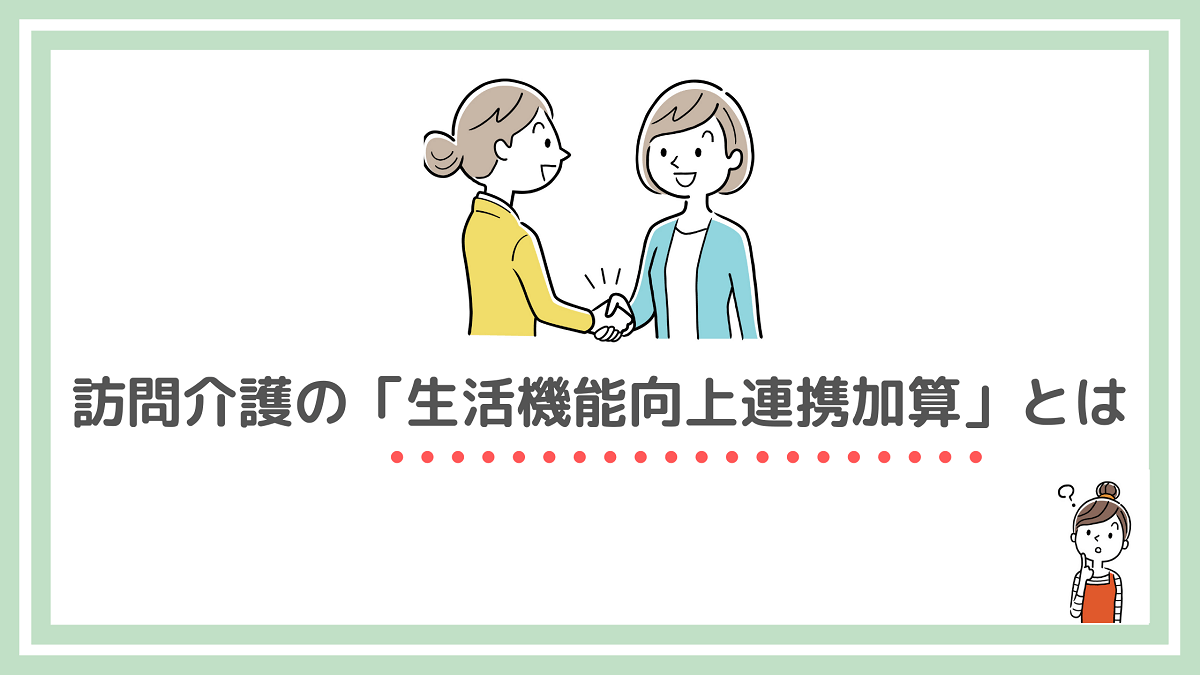訪問介護の「生活機能向上連携加算」ってなに?
リハビリ職と連携していたら算定できるの?
PTさんと関わることも多いので、分かりやすく算定要件を教えてほしい。
こんな疑問を感じている方は多いです。
訪問介護では訪問リハビリなどの職種と関わる機会が多いですよね。
その際に、ある要件を満たすことで生活機能向上連携加算を算定することができます。
詳しく知らない方も多く、本来は算定できたのに見逃していることもあるかもしれません。
そこで今回は
- 生活機能向上連携加算とは?
- 詳しい算定要件と注意点
について初心者の方にも分かりやすく解説していきます。
※本記事は2021年介護報酬改定にも対応している最新版になっています。
【2021年最新】訪問介護の生活機能向上連携加算とは?
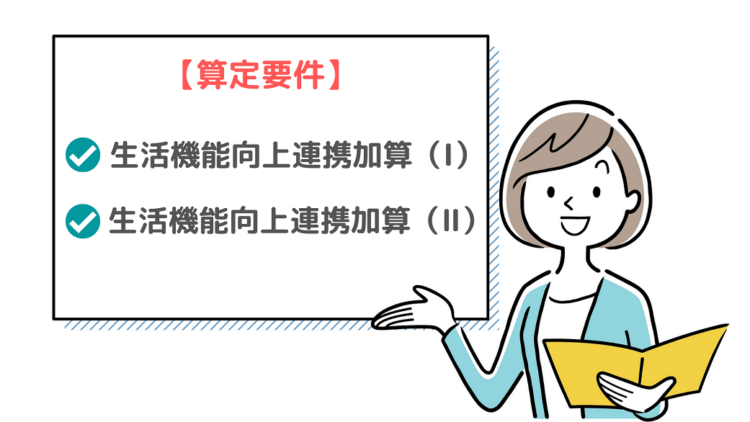
訪問介護の生活機能向上連携加算は、サービス提供責任者が外部の医療機関の理学療法士等と連携して訪問介護計画書を作成した場合に取得できる加算です。
医療提供施設との連携の度合いによって2種に区分されています。
- 生活機能向上連携加算(Ⅰ)・・・100単位
- 生活機能向上連携加算(Ⅱ)・・・200単位

(Ⅰ)(Ⅱ)の詳しい算定要件を見ていきましょう。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)の2つの算定要件
生活機能向上連携加算(Ⅰ)はサービス提供責任者が、外部の医療機関の理学療法士などの助言にもとづいて、訪問介護計画書を作成し、サービス提供した場合に算定できる加算です。
具体的な要件は下記の2つ。
- 医療機関の理学療法士等から助言を受け、生活機能の向上を目的とした計画を作成する
- 目標達成の程度を理学療法士等へ報告する
① 医療機関の理学療法士等から助言を受け、生活機能の向上を目的とした計画を作成する
サービス提供責任者は理学療法士等に、利用者のADLやIADLなどの状態を、ICTを活用した動画やテレビ電話等を用いて伝達し、助言をもらいます。
なお、この際に理学療法士等は利用者宅を訪問する必要はありません。
次に理学療法士等からの助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成します。
訪問介護計画には利用者の能力や機能改善の可能性に応じて、具体的な目標設定・サービス内容を記載しなければなりません。
訪問介護計画に記載すべき事項は下記のとおり。
- 利用者が可能な限り自立しておこなう行為の内容
- 具体的な目標
- 各月に分けて段階的に目標達成できるような設定
- 目標達成のために提供するサービス内容
② 目標達成の程度を理学療法士等へ報告する
訪問介護計画を作成した「3カ月後」に、目標達成の程度を利用者および理学療法士等へ報告する必要があります。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)を「算定」する上での注意点
生活機能向上連携加算(Ⅰ)は初回のサービスを提供した月のみ算定できます。
ただし、初回から3カ月以降であれば、理学療法士等から助言をもらい、新たに訪問介護計画を作成することで再算定が可能となっています。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)の2つの算定要件
サービス提供責任者が、外部の医療機関の理学療法士等が利用者宅を訪問する際に同行をして、評価を共同で行い、訪問介護計画書を作成した場合に算定ができます。
- 医療機関の理学療法士等と共同評価を行い、生活機能の向上を目的とした計画を作成する
- 3カ月間、各月の目標達成の程度を理学療法士等へ報告する
① 医療機関の理学療法士等と共同評価を行い、生活機能の向上を目的とした計画を作成する
医療機関の理学療法士等が利用者宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行し、共同で評価を行います。
次に、共同評価の内容や理学療法士等からの助言を反映し、生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成します。
(※訪問介護計画に記載すべき事項は前述のとおり)
2021年介護報酬改定により、サ責と理学療法士等による共同評価は、利用者・家族も参加する「サービス担当者会議」の前後に時間を明確に区分した上で実施してもOKとなりました。

加算(Ⅰ)は訪問せず助言のみで、加算(Ⅱ)は訪問し共同評価。
② 3カ月間、各月の目標達成の程度を理学療法士等へ報告する
生活機能向上連携加算(Ⅱ)を算定している「3カ月間」は、毎月、目標達成の程度を利用者および理学療法士等へ報告する必要があります。

加算(Ⅰ)は「3カ月後」の報告で、加算(Ⅱ)は「3カ月間」毎月報告。
生活機能向上連携加算(Ⅱ)を「算定」する上での注意点
生活機能向上連携加算(Ⅱ)は初回のサービス提供した月以降の「3カ月間のみ」ひと月ごとに算定が可能です。
要は「3カ月限定」の加算だと認識してください。
3カ月以降も算定する場合は、再度、理学療法士等と共同で評価をおこない訪問介護計画を作成する必要があります。
生活機能向上連携加算(Ⅰ)との併算定はできません。
生活機能向上連携加算の対象となる「医療機関」と「職種」
生活機能向上連携加算の対象となる「医療機関」や「職種」は下記のとおりです。
【医療機関】
- 病院(許可病床数が200勝未満または半径4km以内に診療所がない病院)
- 診療所、クリニック
- 介護老人保健施設
- 介護療養型施設
- 介護医療院
【理学療法士等】
- 理学療法士
- 作業療法士
- 言語聴覚士
- 医師
さいごに
今回は訪問介護における生活機能向上連携加算について解説しました。
訪問介護には他にも様々な加算があります。サービス提供責任者は加算の知識はしっかり得ておきましょう。
下記で訪問介護の『加算・減算』をわかりやすくまとめてますので合わせてチェックしてみてください。
※サービス提供責任者の仕事内容が知りたい方は下記をどうぞ。