
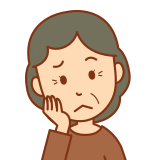
利用者さんに「爪切りしてくれない?」って言われたからしたんだけど
後でサ責に怒られた・・・。爪切りって医療行為なの?
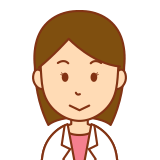
どこからどこまでが医療行為なのかイマイチわからない・・・
分かりやすくまとめてもらえると助かる。

確かに医療行為の範囲ってわかりずらいですよね。
利用者さんは「できるもの」だと思ってヘルパーに依頼してくるし・・・
ということで今回は
- 訪問介護で実施できる医療行為について
- 医療行為ではないと厚生労働省が通達している行為
- ヘルパーが医療行為について注意したい2つのこと
を解説していきます。ぜひご参考ください。
そもそも医療行為ってどんな行為?
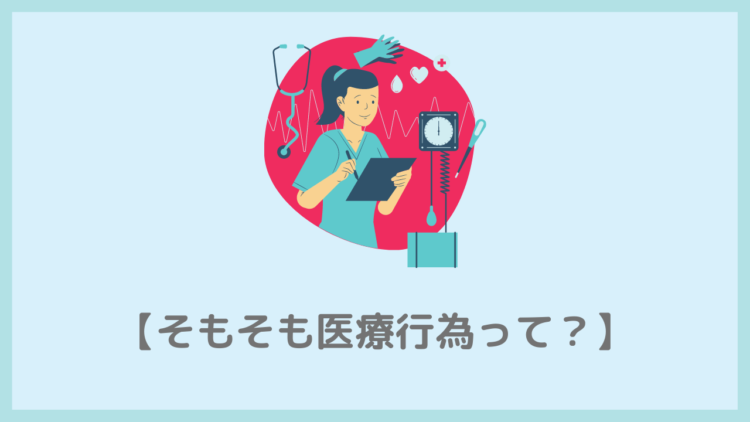
医療行為とは厚生労働省によると下記のように定義されています。
「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」
このように医師ではない訪問介護では原則「医療行為」を実施することはできないということになっています。
訪問介護で実施できる医療行為とは?
前述のとおり、原則訪問介護では医療行為を実施することはできないのですが平成24年4月からの法改正により一定の条件下で、「介護福祉士(平成28年以降の合格者)」と「認定特定行為従事者」にかぎり実施可能となりました。
実施可能となった医療行為は下記の2つです
- 喀痰吸引・・・口腔内、気管カニューレ内部、鼻腔内は咽頭部の手前まで可能。
- 経管栄養・・・胃ろう、腸ろう(医師、看護職員が状態確認を行う)、経鼻経管栄養(医師、看護職員がチューブの挿入状態確認を行う)
厚生労働省が定めている「医療行為ではない」と認められるものとは?
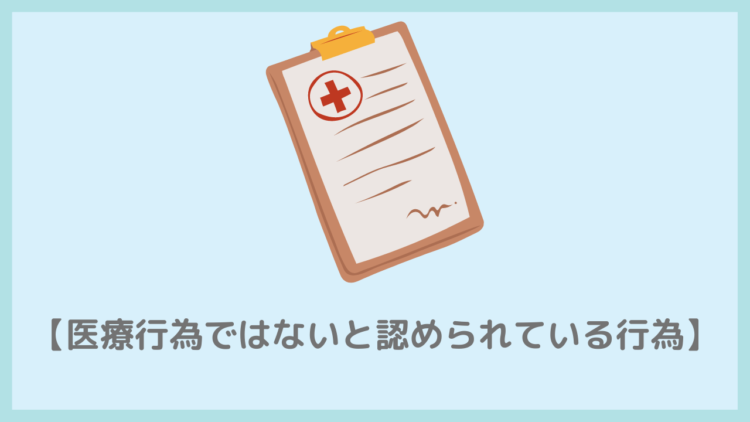
平成17年の厚生労働省通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について」に「医療行為でないと考えられる行為」について示されています。
今回はこの資料をもとに医療行為ではないと認められるものを具体的に解説していきます。
体温測定
水銀体温計や電子体温計を脇に入れての体温測定、耳式電子体温計を外耳道へ入れての体温測定にかぎり訪問介護で実施することを認められています。肛門に体温計を指して直腸の温度を測る行為などは医療行為となりますので要注意です。
血圧測定
訪問介護で自動血圧測定器を使って血圧を測ることのみが認められています。水銀での血圧測定は医療行為に当てはまりますので訪問介護では実施できません。一般家庭でも使うような血圧測定器なら問題なしです。
⇒ヘルパーの血圧測定は医療行為?介護保険制度を再確認してみましょう
パルスオキシメーターで血中酸素濃度を測る
新生児以外で、入院治療が必要でないもの対してのみパルスオキシメーターを使用して血中酸素濃度(SPO2)を測ることができます。
専門的な判断が必要でない軽微な傷の処置
軽微な切り傷、擦り傷、やけど等で医師や看護師による専門的な判断や技術を必要ではない物のみ処置が可能です。また、便等の汚物で汚染されたガーゼの交換等も含まれると通達されています。
内服の補助、肛門からの座薬挿入、皮膚への軟膏の塗布等
下記の3つの条件を満たすことで訪問介護で実施可能となります。
- 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
- 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
- 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
「軟膏の塗布」と「服薬介助」については注意点が他にもありますので下記2記事をご参考ください
爪切り
爪切りについては
- 爪に異常がない
- 爪の周囲に化膿や炎症がない
- 糖尿病等の基礎疾患がない
などの場合のみ訪問介護で「爪切り」や「爪のやすりがけ」を行うことが可能となっています。
>>ヘルパーによる爪切りは医療行為になる?爪切りのルールを確認。
口腔ケア
訪問介護で歯ブラシや綿棒などを使用して口腔内の汚れを取るなどの口腔ケアは実施可能です。
ただし重度の歯周病などがある場合は認められていません。
耳垢を取ること
訪問介護で耳垢を除去することは可能となっています。
ただし耳垢塞栓の除去に関しては認められていません。
ストマのパウチにたまった排泄物を捨てること
訪問介護でストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てることは可能となっています。
自己導尿の補助(カテーテルの準備等)
訪問介護で自己導尿を補助するためにカテーテル準備や体位保持などを行うことは可能となっています。
市販の浣腸を使用すること
訪問介護で市販の浣腸を使用することは認められています。
ただし、
- 挿入部の長さが5~6cm程度、グリセリン濃度50%、
- 成人用の場合で40g程度以下の容量
- 6歳~12歳未満の小児用の場合で20g程度以下の容量
- 1歳~6歳未満の幼児用の場合で10g程度以下の容量
のものに限り可能となっていますので注意しておきましょう。
医療行為の「解釈」に十分な注意をしましょう!

前述に添付したとおり厚生労働省による医療行為についての通達自体をどう解釈するかに注意が必要です。
どういうことかと言うと、例えば人によって「軽微な傷」の解釈が違うということです。この解釈を間違ってしまいますと医療行為をしていないつもりでも医療行為をしてしまう事にもなりかねません。そのため判断が難しい場合は医療行為だと判断しておくのが安心でしょう。
ヘルパーは正しい知識をしっかり持っておかないと危険
医療行為は医師や看護師にしか認められていない行為であり、法律でも明記されています。
ヘルパーができない医療行為行ってしまいますと医師法違反等に問われます。つまり、何が医療行為かを知ることは自分の身を守るものであり、医療行為と密接に関係しているヘルパーは必ず覚えておかないといけないものとなります。
正しい知識は利用者の身を守ると同時に、自分の身も守るものだと覚えておきましょう。
まとめ
今回は医療行為の範囲と注意点を解説しました。
ヘルパーをしていると、どこまでができる行為でどこまでができない医療行為か分からないことも多いと思います。まよったらこの記事をみてください!
また当サイトではホームヘルパー・サービス提供責任者の初心者向けに業務マニュアルを無料で公開しています。
良かったら下記から参考にしてみてください!
※ホームヘルパーはこちら
※サービス提供責任者はこちら






