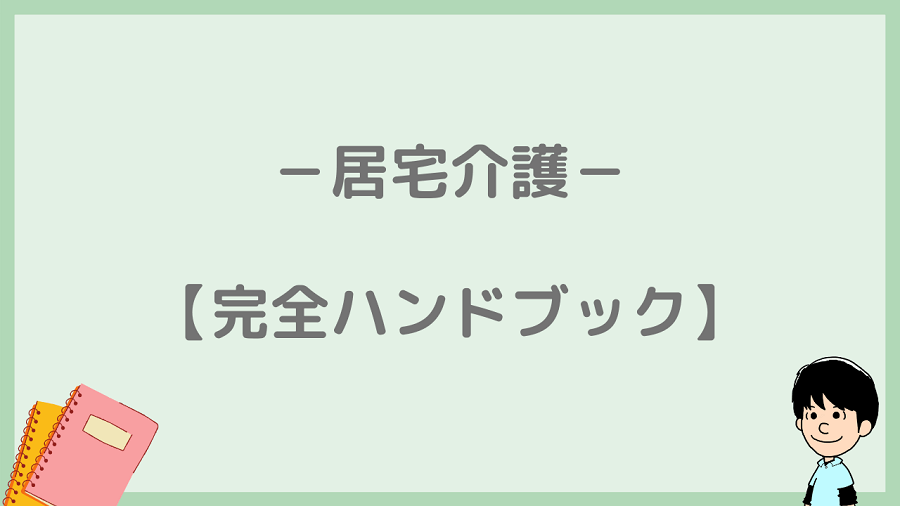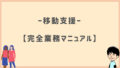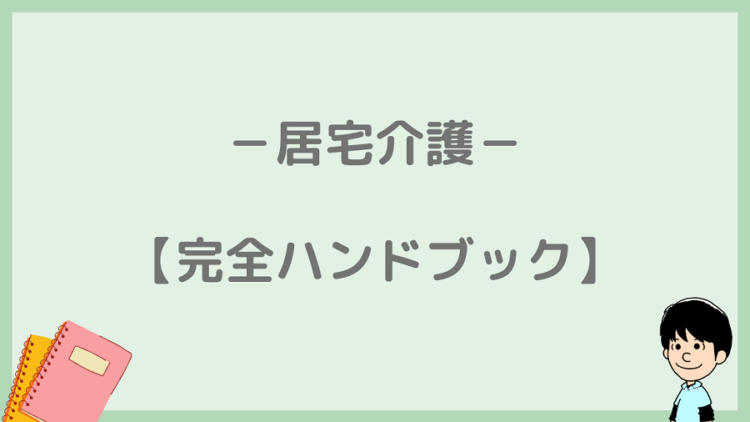
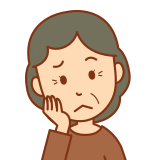
居宅介護って障がい者に対しての訪問介護だよね・・・?
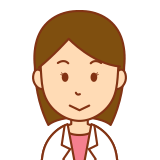
なんとなくは分かっているけど介護保険サービスとなにが違うのかイマイチ分ってない

確かに・・・。居宅介護は介護保険の訪問介護にくらべて認知度は低いかもしれません。
てことで今回は
- 居宅介護で働き始める方
- 居宅介護と訪問介護の違いを知りたい方
- 制度についても詳しく知りたい方
へ向けて、現役介護職のわたしが居宅介護のサービス内容から制度面まで網羅的に学べるハンドブックを作ってみました。ぜひ参考にしてみてください!
※こちらも併せて参考にしてみてください。
障害福祉サービスの居宅介護とは?

居宅介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつに位置づけられています。
厚生労働省によると
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行う」
となっています。
簡単に言うと障害福祉バージョンの訪問介護なのですが、介護保険のサービス内容とは少し異なる部分があります。
居宅介護サービスの内容を具体的に解説

前述のとおり、居宅介護は介護保険の訪問介護とは少し異なるところがありますので、そのあたりを含めてサービス内容を具体的に解説していきます。
基本的に居宅介護では下記4つのサービスを提供します。
- 身体介護
- 家事援助
- 通院等介助
- 通院等乗降介助
です。それぞれ深掘りしていきましょう。
① 身体介護
居宅介護の身体介護では
などのサービスを提供します。
ちなみに一連の行為に関わる全般が身体介護の範囲になります。(例えば食事介助のための食事準備や後片付けなど)
そのほか、医療行為は行うことはできませんので注意しておきましょう。医療行為については下記で詳しく解説してますのでご参考ください。
>> 訪問介護で実施できる医療行為とは?範囲と注意点を解説。
② 家事援助
居宅介護の家事援助は本人が行うことができない、または家族によるサポートも困難、という場合に支援を行うことができます。
具体的には
- 普通食の調理
- 整理整頓
- 洗濯
- 掃除
- 買い物
- 処方薬の受け取り
- 代読、代筆
- 育児支援
などを行います。
育児支援は介護保険では無いサービスになります。
育児中の障害者に対し、必要だと認められた場合には育児支援を行うことができます。
育児支援の例を挙げると・・・
- 利用者の子供に対しての食事(授乳)や掃除、洗濯
- 通園または通学の為の送迎あるいは送迎補助
- その他子供の健康管理や発育の補助
このような支援が認められています。
>>障害福祉サービスの居宅介護で「家事援助」はどこまで提供できる?
③ 通院等介助
居宅介護の通院等介助では
- 病院への通院介助
- 官公署への公的手続き
- 障害福祉サービスにおける指定相談支援事業所へ相談に行く
など病院以外にもヘルパーによる外出介助が可能となっています。
また通院等介助のサービス区分は
- 身体介護を伴う
- 身体介護を伴わない
の2つに分けれています。障害福祉サービス受給者証に記載されていますので確認しておきましょう。
④ 通院等乗降介助
通院等乗降介助ではヘルパーが運転する車で送迎するサービスをおこないます、
乗車・降車のさいに支援が必要かつ、病院などの窓口で、ヘルパーが手続きを行う必要がある場合に通院等乗降介助を提供することができます。
その他の援助
居宅介護のその他の援助として、相談援助や情報収集があげられます。
生活していく上での悩みの相談に対する助言、介護にまつわる公的サービスなどの情報収集の援助を行います。
居宅介護計画書にもとづいたサービス提供を
居宅介護サービスを提供するにあたって、居宅介護計画書を作成しておく必要があります。
居宅介護計画書には
- 利用者氏名
- 生年月日、住所、連絡先
- 本人または家族の希望
- 援助目標
- サービス内容、手順、所要時間
- 支給決定時間
- サービス計画予定
などを記載します。
この居宅介護計画書にもとづきサービス提供をしていき、変更があった場合は再作成します。
なお、定められたフォーマットはありませんので事業所独自の書式を使用します。
当サイトが独自に開発したフォーマットを下記からダウンロードできますので欲しい方はどうぞ。
居宅介護サービスを利用できる対象者は?
居宅介護の利用要件は厚生労働省によると下記のとおり。
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、次のいずれにも該当する支援の度合(障害児にあっては、これに相当する支援の度合)であること
(1) 障害支援区分が区分2以上に該当していること
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
となっています。
障害支援区分1は最も軽度な介助量の方ということです。障害支援区分が非該当にならない限り、居宅介護を受けることができます。ただし、2にあるように、「通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合」は障害支援区分が区分2以上でさらに(2)のように細かい規定があり、やや対象者が限られてきます。
居宅介護サービスの介護報酬
居宅介護の介護報酬は、サービスコード×地域単価で計算することができます。
- サービスコード・・・身体介護や家事援助、通院等介助の1回分の単位数を示したもの。
- 地域単価・・・地域ごとの1単位の値段をしめしたもの
下記を参照ください。
例えば、大阪市の事業所で日中に身体介護1時間を月8回提供した場合
大阪市は2級地なので地域単価は10.96円
日中の身体介護1時間は402単位
なので402×8×10.96=35,247円
といったように介護報酬は計算されます。

ちなみに、加算を取得している事業所の場合、この金額に加算がプラスされます。
居宅介護の制度面で注意しておきたい6つのこと
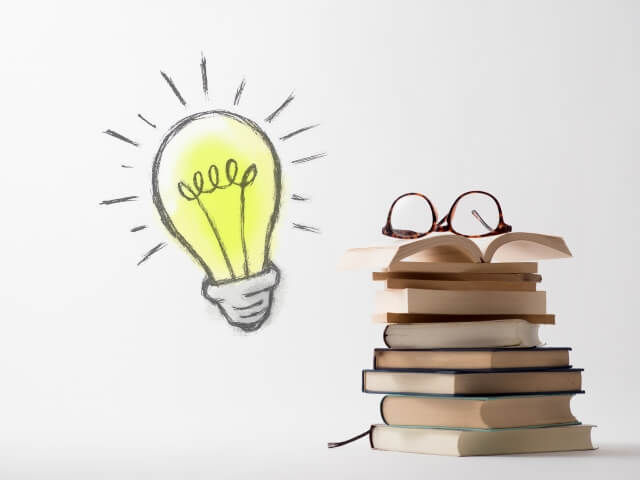
この章では障害福祉サービスの居宅介護における制度面について注意してほしいところ6つ紹介しておきます。
以下の通りです。
- 通院や公的機関以外の「外出支援」について
- 「経済活動」は認められない
- 「2人介助」について
- 「見守り的援助」について
- 「65歳になった場合」に対応について
- 「見守りのみ」や「留守番」はNG
それぞれ確認していきましょう!
①通院や公的機関以外の「外出支援」について
通院等介助の章でも解説しましたが
- 病院への通院介助
- 官公署への公的手続き
- 障害福祉サービスにおける指定相談支援事業所へ相談に行く
を対象としたサービスになっています。
なので余暇活動などを目的とした利用はできません。
余暇活動を行いたい場合は地域生活支援事業の移動支援を利用することになります。
なお、買い物同行についても介護保険の訪問介護であれば身体介護で算定しますが、居宅介護では多くの自治体で身体介護の算定ができません。(見守り的援助によるものを除く)家事援助での算定または移動支援での算定など自治体によりさまざまですので注意しておきましょう。
>>居宅介護の買い物同行は身体介護?家事援助?どちらで算定すべきか
②「経済活動」は認められない
原則、経済活動に関することは認めれません。
通院等介助でも利用できませんし、外出ではなくとも、自宅内での内職などの支援についても認められていません。
③「2人介助」について
居宅介護の利用者の中には2人介助ではないと対応できないケースもあります。
2人介助として算定するための要件は、厚生労働省によると下記のとおりです。
- 障害者等の身体的理由により一人の従業者による介護が困難と認められる場合
- 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合
- その他障害者等の状況等から判断して、第一号又は前号に準ずると認められる場合
と、なっていますのでしっかり押さえておきましょう。
>> 訪問介護の「2人介助加算」とは?算定要件と5つの注意点
④「見守り的援助」について
見守り的援助とは、正式には「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」と言い、介護保険の訪問介護において、利用者の自立支援、ADL・IADL・QOL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等を行う身体介護サービスです。
この見守り的援助が、障害福祉サービスの居宅介護にも適用されるかどうかは自治体の取り扱いにより異なります。そのため介護保険と同様に見守り的援助を身体介護で算定できる地域もあれば、家事援助でしか算定できない地域もありますので、市町村等へ確認しましょう。
>>【居宅介護の共同実践】見守り的援助は障害福祉サービスにも適用されるのか?各市町村の取り扱い状況を調査しました。
④「65歳になった場合」について
居宅介護の利用者が65歳になった場合は基本的に介護保険サービスに切り替わります。
法的に障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先されるためです。
どういった流れで介護保険サービスに切り替わるのか?併用できないのか?について下記で詳しく解説してますので参考にしてみてください。
⑤「見守りだけ」「留守番」もNG
居宅介護は見守りのみや利用者が外出している間の留守番という行為はサービスとして認められていません。
訪問介護では本人不在はあるあるです。下記で詳しく解説してますのでご参考まで。
>>訪問介護でよくある「本人不在」。留守時はどうする?対応方法を解説。
まとめ
今回は障害福祉サービスのひとつである居宅介護の完全ハンドブックを作成しました。
解説した通り、介護保険の訪問介護とは異なる部分もけっこうあります。理解を深めてサービス提供に臨みましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。