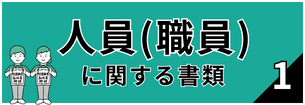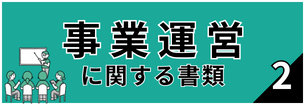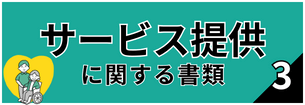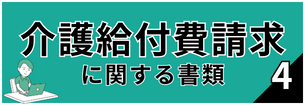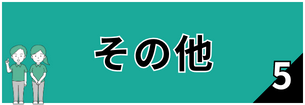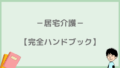訪問介護事業を運営しているのですが、必要な書類が多すぎて困っています…。
どんな書類を揃えておけばいいのでしょうか?
今回はこんな悩みにお答えします。
指定訪問介護事業者は、利用者に対して質の高いサービスを提供することと同時に、それを支える帳票書類を確実に整備しておかなければなりません。
とはいえ、日々忙しい業務の中で膨大な書類を揃えるのはなかなかに至難のワザです。しかも、そもそもどういった書類が必要なのか、イマイチ理解できずお困りの方が多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、訪問介護の事業運営において必要な書類44種をすべて解説します。必要書類の整備は、行政からの実地指導(運営指導)対策としても非常に重要なことですので、ぜひ参考にしてください。
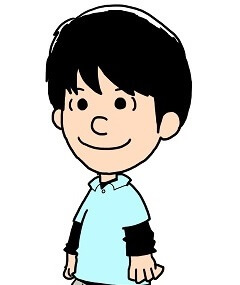
本記事で紹介する書類のうち、利用者個人ファイルに挟んで運用するものについては、以下のコラムで詳しく解説しています。
※本記事は、厚生労働省令および介護保険施設等運営指導マニュアル、各自治体のガイドライン、ヘルパー会議室運営部の調査および実体験等をもとに作成しています。できる限り正確な記述に努めていますが、各自治体のローカルルールや独自の取り扱いを等を含むものではありません。本記事はあくまで参考程度にお考えいただき、各自治体に確認のもと日々の運用を行ってください。
【44種】訪問介護で揃えておく必要書類一覧
本記事では、指定訪問介護の事業運営において揃えておく必要書類を、以下5つの項目に分類しました。
項目ごとに各種書類を解説していきます。
\ クリックすると知りたい所から読めます /
人員(職員)に関する必要記録
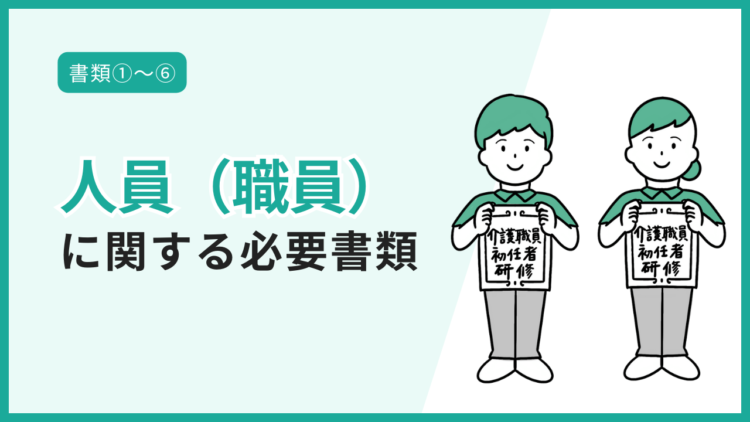
- 勤務関連書類
- 雇用契約書
- 秘密保持誓約書
- 就業規則
- 健康診断の記録
- ハラスメント対策の実施状況が分かる資料
①勤務関連書類
| 概要 | 指定訪問介護は、基準省令第5条・6条に示されている訪問介護員等の員数やサービス提供責任者・管理者の配置基準を常に満たし続けなければなりません。これを証明する根拠書類として主に以下の書類を整備しておきます。
など |
|---|---|
| 基準省令 | (訪問介護員等の員数) 第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、二・五以上とする。 第2項~6項省略 (管理者) |
| ひな形テンプレート |
②雇用契約書
| 概要 | 指定訪問介護は、雇用契約、労働者派遣法に規定する労働者派遣契約その他の契約により、当該事業所の管理者の指揮命令下にある訪問介護員等によってサービスの提供が行われなければなりません。これを証明する根拠書類として雇用の形態がわかる文書(雇用契約書等)を整備しておきます。
(※ちなみに、喀痰吸引等の特定行為を行う訪問介護員等については、労働者派遣法にもとづく派遣労働者であってはならないことされています。) |
|---|---|
| 基準省令 | (勤務体制の確保等) 2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
③秘密保持誓約書
| 概要 | 指定訪問介護事業所は、従業者に対して利用者や家族の秘密情報を漏らしてはならない旨の書(秘密保持誓約書等)を取り交わしておかなければなりません。なお、秘密保持誓約書には退職後も秘密を漏らしてはならない旨の規定を設ける必要があります。 |
|---|---|
| 基準省令 | (秘密保持等) 第三十三条 指定訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
④就業規則
| 概要 | 事業所の従業者がパートタイマーも含めて常時10名以上いる場合は、就業規則を作成し、所管の労働基準監督署へ届け出る必要があります。(常時10名に満たない場合は就業規則の作成義務はありません) |
|---|---|
| 労働基準法 | (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 |
⑤健康診断の記録
| 概要 | 特定事業所加算を取得している事業所は、すべての訪問介護員等に対して、事業主の費用負担で健康診断を定期的に実施(少なくとも1年以内ごとに1回)しなければならず、健康診断の結果を書面にて保管します。また特定事業所加算を取得していない事業所であっても、自治体によっては、基準省令第31条の観点から健康診断の記録の保管を求められる場合があります。 |
|---|---|
| 基準省令 | (衛生管理等) 第三十一条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 |
⑥ハラスメント対策の実施状況が分かる資料
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、法人として性的言動、優越的な関係を背景とした言動による就業環境が害されることの防止に向けた対策を講じる必要があり、主に以下の書類を整備しておきます。
など |
|---|---|
| 基準省令 | (勤務体制の確保等) 第三十条4 指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 |
事業運営に関する必要書類

- 運営規程
- 研修に関する記録
- 身分を証する書類
- 苦情相談に関する記録
- 事故に関する記録
- 各種マニュアル
- 虐待の防止に関する措置に関する書類
- 業務継続に向けた取り組みに関する書類
- 感染症の予防及びまん延の防止のための対策に関する書類
- 会計関係書類
- 質の評価に関する書類
- 市町村等への通知に係る記録
- 通院等乗降介助に関する書類
⑦運営規程
| 概要 | 指定訪問介護事業所は、適正な事業運営および利用者に対する適切なサービスの提供を確保するため、重要事項の規程を定めておかなければなりません。具体的には以下の項目についてそれぞれを作成します。
※なお同一敷地内で複数のサービス種類について事業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う場合においては、一体的に作成することも差し支えないとされています。 |
|---|---|
| 基準省令 | (運営規程) 第二十九条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
⑧研修に関する記録
| 概要 | 指定訪問介護事業所は、訪問介護員等の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内研修への参加の機会を計画的に確保しなければなりません。これを証明するものとして主に以下の書類を整備しておきます。
など ※研修記録、研修参加表などには、勤務スケジュールの都合などで不参加者がでた場合に補講の状況がわかるように記載しておきましょう。また、特定事業所加算を算定する場合は、すべての訪問介護員等に対する個別の研修スケジュールを定めた計画を作成する必要があります |
|---|---|
| 基準省令 | (勤務体制の確保等) 第三十条3 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。 (管理者及びサービス提供責任者の責務) 第二十八条3 サービス提供責任者は、第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
⑨身分を証する書類
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、利用者が安心して指定訪問介護の提供を受けられるよう、訪問介護員等に身分を明らかにする証書や名札等を携行させなければなりません。吊り下げ名札などをヘルパーひとりひとりに渡しておき、初回訪問時や利用者・家族から求められた際に提示するよう指導します。
※名札には、訪問介護事業所の名称や訪問介護員等の氏名を記載し、顔写真の貼付や職能の記載を行うことが望ましいとされています。 |
|---|---|
| 基準省令 | (身分を証する書類の携行) 第十八条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
⑩苦情相談に関する記録
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、利用者や家族から苦情を受け付けた際に、苦情の受付日、内容、対応等を記録しておかなければなりません。これを証明するものとして以下の根拠書類を整備しておきます。
など |
|---|---|
| 基準省令 | (苦情処理) 第三十六条 2 指定訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
※当サイトの様式は、苦情受付簿と対応記録を兼ねるものとなっています。 |
⑪事故に関する記録
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、訪問介護サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村や利用者の家族、居宅介護支援事業者(ケアマネ)等に対して連絡を行う等の必要な措置を講じるべきこととするとともに、当該事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければなりません。加えて、事故の再発防止策を検討・実施する必要があります。これを証明する根拠として以下の書類を整備しておきます。
など ※また事故防止のため、日々の業務中でヒヤリハット記録等を作成し、研修等へ共有しておくと良いでしょう。ヒヤリハット記録も実地指導(運営指導)時に確認される場合があります。 |
|---|---|
| 基準省令 | (事故発生時の対応) 第三十七条 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
※当サイトの事故報告書の様式は、家族や関係機関への連絡、事故対応、再発防止策の検討を兼ねるものとなっています。(家族やケアマネ等の関係機関への報告内容等は、別途記録様式を設けるか支援経過記録等へ併せて記録してください) |
⑫各種マニュアル
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、基準省令「第27条(緊急時等の対応)」、「第31条(衛生管理)」「第36条(苦情処理)」、「第37条(事故発生時の対応)」の観点から以下のマニュアルを整備しておく必要があります。
※上記にうち衛生(感染症)マニュアルは厚生労働省の実地指導確認項目にのっていませんが、整備を求める自治体が多いため基本的には作成しておいてください。 また介護サービス情報公表制度により、以下のマニュアルの作成を求められています。
※これらは法令上の必須マニュアルではないため、作成していなくても問題はありません。 |
|---|---|
| 基準省令 | (緊急時等の対応) 第二十七条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 (衛生管理等) 第三十一条 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。 その他、第三十六条、第三十七条は省略 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
※当サイトの事故・緊急時対応マニュアルは、事故対応と緊急時対応を兼ねるものとなっています。 |
⑬虐待の防止に関する措置に関する書類
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、虐待の発生またはその再発を防止するために、虐待防止検討委員会の定期的な開催や指針の作成、研修の実施を求められており、この証明として以下の根拠書類を整備しておきます。
など ※虐待防止委員会は定期的(回数の定めはなし)な開催、研修は年1回以上の実施が必要です。 |
|---|---|
| 基準省令 | (虐待の防止) 第三十七条の二 指定訪問介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 二 当該指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。 三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 |
| 参考コラム |
⑭業務継続に向けた取り組みに関する書類
| 概要 | 指定訪問介護事業所は、感染症や非常災害の発生時において、訪問介護サービスの提供を継続的に実施(およびび早期に業務再開)するために業務継続計画(BCP)を策定し、研修・訓練を実施しなければなりません。この証明として以下の根拠書類を整備しておきます。
など ※業務継続計画は、感染症と災害発生時のものを一体的に作成しても問題ありません。 |
|---|---|
| 基準省令 | (業務継続計画の策定等) 第三十条の二 指定訪問介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 3 指定訪問介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 |
⑮感染症の予防及びまん延の防止のための対策に関する書類
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、感染症および食中毒の発生およびまん延しないよう、感染対策委員会の設置・開催や指針の作成、定期的な研修・訓練を実施しなければなりません。この証明として以下の根拠書類を整備しておきます。
など ※感染対策委員会の設置にあたっては、構成メンバーの責任および役割分担を明確にするとともに、専任の感染対策を担当する者(感染対策担当者)を決めておく必要があります。 |
|---|---|
| 基準省令 | (衛生管理等) 第三十一条3 指定訪問介護事業者は、当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。 二 当該指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。 三 当該指定訪問介護事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。 |
⑯会計関係書類
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、事業ごとに会計を区分しなければなりません。これは、例えば、訪問介護事業と自費サービスや訪問系障害福祉サービス(居宅介護や重度訪問介護など)を一体的に運営している場合は、それぞれの事業ごとに収入・経費・利益を分けて損益計算書を作成するということです。
代表的な会計関係書類には、以下のものがあげられます。
など |
|---|---|
| 基準省令 | (会計の区分) 第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 |
⑰質の評価に関する書類
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、利用者へのサービス提供に係る質の評価を実施しなければなりません。例えば、管理者・サービス提供責任者・訪問介護員等ごとの技術や能力を評価するシートを作成して実施したり、利用者へのアンケート調査を実施したりしたものを保管しておきます。
など |
|---|---|
| 基準省令 | (指定訪問介護の基本取扱方針) 第二十二条2 指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
⑱市町村等への通知に係る記録
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、利用者が故意に要介護状態を悪化させた場合や、不正に保険給付を受けた場合に市町村に通知しなければなりません。一般的に市町村へ報告する機会は滅多にないと考えられますが、通知を行った場合は記録を保管しておいてください。 |
|---|---|
| 基準省令 | (利用者に関する市町村への通知) 第二十六条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 一 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。 |
⑲通院等乗降介助に関する書類
| 概要 | 通院等乗降介助を算定する場合は、道路運送法上の許可・登録が必要です。主に以下の書類を整備しておきます。
など |
|---|---|
| 参考コラム |
⑳喀痰吸引等に関する書類
| 概要 | 指定訪問介護事業者において、たんの吸引や経鼻経管栄養などの特定行為を実施算定する場合は、以下の書類を整備しておく必要があります。
など |
|---|---|
| 厚生労働省Q&A | H24Q&A Vol.1 問119より抜粋
H24Q&A Vol.1 問120より抜粋
|
サービス提供に関する必要書類

- 緊急連絡票
- 相談受付票
- 介護保険被保険者証・負担割合証の写し
- 契約書・重要事項説明書
- 個人情報使用の同意書
- 居宅サービス計画(ケアプラン)
- サービス担当者会議の記録
- アセスメントシート
- 訪問介護計画書
- サービス指示書(手順書)
- 見取り図
- モニタリングシート
- 支援経過記録
- 鍵預かりに関する記録
㉑緊急連絡票
| 概要 | 緊急連絡票は、サービス中に利用者の体調が急変した場合などに、「どこにどのような順番で連絡するのか」を定める書類です。主に、利用者の氏名やキーパーソン、既往歴、服薬状況、主治医、搬送先の指定病院、緊急時の連絡順序などを記載しておき、有事の際は緊急連絡票をもとに対応していきます。
※事業所(個人ファイル)用と利用者宅用の2部整備しておきましょう。 |
|---|---|
| 基準省令 | (緊急時等の対応) 第二十七条 訪問介護員等は、現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
㉒相談受付票
| 概要 | 相談受付票は、訪問介護サービスの利用申し込みがあった場合に、必要事項を記録する書類です。指定訪問介護事業者は、要介護度や所得の多寡を理由にサービス提供を拒否できず、原則として利用申し込みに応じなければならないと規定されています。
指定訪問介護事業者がサービス提供を拒否できる正当な理由は、以下の3つのいずれかに該当する場合です。 ①当該事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合 ※相談受付票は、利用申し込みを受ける・受けないに関わらず作成してください。 |
|---|---|
| 基準省令 | (提供拒否の禁止) 第九条 指定訪問介護事業者は、正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
㉓介護保険被保険者証・負担割合証の写し
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、訪問介護サービスの提供の開始に際して、被保険者資格や要介護認定の有無および要介護認定の有効期間を確認することを義務付けられており、被保険者証等のコピーを保管しておきます。
※本来はコピーの保管義務はないため介護請求ソフト上で確認できれば問題ありません。 |
|---|---|
| 基準省令 | (受給資格等の確認) 第十一条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 |
| ひな形テンプレート |
㉔契約書・重要事項説明書
| 概要 | 契約書と重要事項説明書を取り交わしてから、利用者に対する訪問介護サービスの提供を開始します。重要事項説明書には、運営規程の概要や訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、第三者評価の実施状況などを記載します。
※重要事項説明書と「⑦運営規程」の内容に相違がないよう注意してください。 |
|---|---|
| 基準省令 | (内容及び手続の説明及び同意) 第八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 |
| 社会福祉法 | (利用契約の成立時の書面の交付) 第七十七条 社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 一 当該社会福祉事業の経営者の名称及び主たる事務所の所在地 二 当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容 三 当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 四 その他厚生労働省令で定める事項 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
㉕個人情報使用の同意書
| 概要 | 個人情報使用の同意書は、サービス担当者会議等においてケアマネジャーや他サービス事業所との間で個人情報を共有することに対して同意をもらうための書類です。一般的に、契約時に契約書や重要事項説明書と一緒に説明して同意書を取り交わします。
※個人情報使用の同意書には、利用者だけでなく家族の同意欄も設けるようにしてください。 |
|---|---|
| 基準省令 | (秘密保持等) 第三十三条3 指定訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
㉖居宅サービス計画(ケアプラン)
| 概要 | 居宅サービス計画(ケアプラン)は、利用者に関わるサービス全体の援助計画で、ケアマネジャーが作成し、利用者や各サービス担当者に交付されます。
訪問介護は、原則として居宅サービス計画に位置づけられていないサービス内容の提供ができません。また、居宅サービス計画に沿って㉙訪問介護計画書を作成しますので、ケアマネジャーから交付を受けたら利用者個人ファイルにて保管しておきます。(受領書がある場合は、同様に保管) |
|---|---|
| 基準省令 | (居宅サービス計画に沿ったサービスの提供) 第十六条 指定訪問介護事業者は、居宅サービス計画(施行規則第六十四条第一号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 |
㉗サービス担当者会議の記録
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、基準省令第13条および第28条第3項の三の観点からサービス担当者会議に出席する度に記録を整備しておかなければなりません。
基本的にはケアマネジャーが作成する居宅サービス計画の第4表「サービス担当者会議の要点」を保管していれば問題ないと考えますが、ケアマネジャーに第4表をサービス事業所に交付する義務はありません。そのため、貰えない場合は、別途様式に記録する、あるいは支援経過記録等に記録するなどで対応します。 また、サービス担当者会議が開催されない、または欠席した場合などであって、「照会」にて対応する場合は、照会書類もあわせて保管しておきましょう。 |
|---|---|
| 基準省令 | (心身の状況等の把握) 第十三条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。(居宅介護支援事業者等との連携) 第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。 |
㉘アセスメントシート
| 概要 | アセスメントシートは、利用者の日常生活全般の状況や希望、課題分析などを記録する書類です。ケアマネジャーが作成するアセスメントシート等で代替することはできません。訪問介護の目線から訪問介護サービスによって解決すべき問題の状況を明らかにした内容を記入してください。
※訪問介護のアセスメントシートに定められた様式はありません。 |
|---|---|
| 基準省令 | (訪問介護計画の作成) 第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
㉙訪問介護計画書
| 概要 | 訪問介護計画書は、その利用者に対する援助目標や担当する訪問介護員等の氏名、具体的なサービス内容、所要時間、日程等を記入する書類です。基本的にケアマネジャーから居宅サービス計画が交付される度に、当該居宅サービス計画に沿って作成・更新します。
※訪問介護計画書に定められた様式はありません。 |
|---|---|
| 基準省令 | (訪問介護計画の作成) 第二十四条 サービス提供責任者(第五条第二項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この条及び第二十八条において同じ。)は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問介護計画を作成しなければならない。 2 訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 3 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。 4 サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。 5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 6 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する訪問介護計画の変更について準用する。 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
㉚サービス指示書(手順書)
| 概要 | サービス指示書は、サービス提供開始から終了までの支援の具体的な内容や手順を記入する個別マニュアルのような書類です。訪問介護計画書で示したサービス内容を補完する役割もありますので、訪問介護計画書の作成・更新に合わせてサービス指示書も作成・更新してください。 |
|---|---|
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
㉛見取り図
| 概要 | 見取り図は、利用者宅内の構造を可視化する書類です。居室、トイレ、風呂がどこにあるか、だけではなく「使用する物品の場所」や「段差の高さはどの程度なのか?」「手すりはついているのか?」などを具体的に記入します。
※見取り図は、アセスメントシート内の項目にまとめたり、サービス指示書と一体的に作成したりするのも良いでしょう。 |
|---|---|
| ひな形テンプレート |
㉜モニタリングシート
| 概要 | モニタリングシートは、訪問介護サービスの実施状況を把握し、訪問介護計画に位置づけた援助目標の達成度や利用者の満足度を評価した内容を記入する書類です。モニタリングの頻度に定めはありません。毎月行っても良いですし、3ヵ月に1回程度の実施でも良いです。ただ最低でも目標期間の更新時期にあわせて実施し、その結果を記録して保管してください。
※基準省令上、モニタリングシート(報告書)をケアマネジャーに提出する義務はありませんが、居宅サービス計画の見直しにもつながるものですので、モニタリングの実施後は提出しておきましょう。 |
|---|---|
| 基準省令 | (訪問介護計画の作成) 第二十四条5 サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 |
| サービス実施状況報告書について | 事業所によっては、サービス実施状況報告書を毎月ケアマネジャーに提出しているところもあるかと思いますが、本来、訪問介護事業所にサービス実施状況報告書なる書類の作成および提出義務はありません。
ただし、ケアマネジャーから求められる場合が多いことや、基準省令第28条第3項二の二に「利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと」を求められていることから、定期的に提出しておいた方が良いでしょう。 もっとも前者・後者ともにサービス実施状況報告書なる書面ではなく、FAX送付状など簡易的なものに記載して報告提出することで足りますし、後者についてはサービス担当者会議での報告で差し支えありませんので、事業所にとって効率的な方法で運用してください。 |
| 総合事業の場合 | 総合事業(指定相当)については、訪問介護とモニタリングの規定が異なるため注意が必要です。
総合事業の場合は、計画期間が終了するまでに少なくとも1回はモニタリングを実施して結果を記録し、ケアマネジャーに報告します。加えて、ケアマネジャーに対して、毎月、利用者の状態やサービス提供状況等の報告を行う必要があります。 |
| 基準省令(総合事業) | 第四十条 訪問介護員等の行う指定相当訪問型サービスの方針は、第三条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱い方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
一~十は省略 十一 サービス提供責任者は、訪問介護相当サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該訪問介護相当サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画等を作成した介護予防支援事業者等に報告するとともに、当該訪問介護相当サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該訪問介護相当サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。 十四省略 |
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
※当サイトでは、モニタリングシートとサービス実施状況報告書を兼ねるものと、別々のものを用意しています。自治体の取り扱いや事業所の運用方針により使い分けてください。 |
㉝支援経過記録
| 概要 | 支援経過記録とは、相談受付から支援終了までの経過を時系列で記録する書類です。
基準省令上の必須書類ではありませんが、その他の必須書類を補完する役割もありますので必ず作成しておきましょう。具体的には以下の項目について記録します。
など ※FAXでケアマネジャー等とやり取りした場合(相談・報告等)は、支援経過記録に綴じ込むなどFAX用紙を捨てずに保管しておいてください。(メモ用紙なども同様) |
|---|---|
| 参考コラム | |
| ひな形テンプレート |
㉞鍵預かりに関する記録
| 概要 | 利用者宅の鍵を訪問介護事業所で預かる場合に、必要な書類は以下のとおりです。
※鍵預かり書・返却書は2部作成して利用者・事業所双方で保管してください。 |
|---|---|
| ひな形テンプレート |
㉟身体拘束等に係る記録記録
| 概要 | 令和6年度介護報酬改定により、身体的拘束等の更なる適正化を図る観点から、省令が改正され、緊急やむを得ない場合に身体拘束等を行う場合は、以下の記録を作成することを義務付けられました。
※身体拘束等を行う事案がない場合であっても様式は整備しておきましょう。 ※身体拘束等を行う場合の記録に記載する項目のうち、「緊急やむを得ない理由」は、切迫性・非代替性・一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行い、その具体的な内容について記録しておくことが必要です。 |
|---|---|
| 基準省令 | (指定訪問介護の具体的取扱方針) 第二十三条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。 三 指定訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。 四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 |
介護給付費請求に関する必要書類

- サービス提供票・別表
- 介護券
- 介護給付費請求書・明細書の控え
- 利用者への請求書・領収書の控え
- サービス提供証明書の控え
㊱サービス提供票・別表
| 概要 | サービス提供票は、毎月の月初にケアマネから交付される訪問介護サービスの予定表を指し、別表には介護給付費の情報が記載されています。
また、その月のサービスが終了後には、サービス提供票の実績欄に「1」(実績を示す数字)と記入し、ケアマネへ実績報告(提供票の提出)を行います。 |
|---|---|
| 参考コラム |
㊲介護券
| 概要 | 介護券は、生活保護を受給している利用者に対してサービス提供を行う場合に、市役所または福祉事務所から発行される書類です。国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に提出する介護給付費請求書・明細書を作成する際に、介護券に載っている公費受給者番号や負担者番号等が必要になります。
※介護券は、ケアマネジャーが生活保護担当へ居宅サービス計画を提出することで訪問介護事業者に自動的に送られてきます。 |
|---|
㊳介護給付費請求書・明細書の控え
| 概要 | 介護給付費請求書は、当該保険者へ請求をあげる請求をあげる全利用者分の合計金額などを記載する書類で、明細書は、各利用者ごとの詳細を記載する書類です。これらの書類を、毎月1日~10日までに国保連へ提出することで、介護給付費が事業所へ支払われます。
※介護給付費請求書・明細書は共通の様式が定められており、訪問介護の場合は、介護給付費請求書は「様式第一」、居宅サービス・地域密着型サービス介護給付費明細書は「様式第二」になります。 ※各種加算を算定請求する場合は、根拠となる挙証資料を整備しておく必要があります。 |
|---|---|
| 参考コラム |
㊴利用者への請求書・領収書の控え
| 概要 | 国保連への請求業務完了後に、利用者へ請求書を発行して利用料を徴収、支払いを受けたら領収書を発行します。請求書・領収書は、保険給付の対象サービスと介護保険外サービスの費用を明確に区分して作成してください。加えて、当該サービスが医療費控除の対象である場合は、対象金額を記載します。
※医療費控除の対象となるのは、介護保険制度下の医療系サービス(訪問看護や訪問リハ、居宅療養管理指導など)などと併せて訪問介護を利用する場合の身体介護中心型等のサービスです。生活援助中心型サービスについては医療費控除の対象となりません。詳細は以下の国税庁HPを参照してください。 参考:国税庁HP |
|---|---|
| 厚生労働省事務連絡 | (問) 介護職員処遇改善加算が創設されたが、訪問介護において身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取り扱うか。
(答) 訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となるとされているところです。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関 厚生労働省「介護保険制度下での訪問介護等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」より抜粋 |
㊵サービス提供証明書の控え
| 概要 | サービス提供証明書は、法定代理受領サービスに該当しない訪問介護サービスを提供した場合に利用者へ交付する書類です。㊲の明細書と同じような内容が記載されており、利用者が償還払いを受ける際に必要になります。 |
|---|---|
| 基準省令 | (保険給付の請求のための証明書の交付) 第二十一条 指定訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 |
その他の必要書類

- 事業所の平面図、備品台帳
- 賠償責任保険関係書類
- 指定関係書類の写し
- 自主点検表
㊶事業所の平面図、備品台帳
| 概要 | 基準省令第7条(設備に関する基準)を満たしているかを確認するために平面図や設備、備品台帳を整備しておく必要があります。 |
|---|---|
| 基準省令 | (設備及び備品等) 第七条 指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 |
| ひな形テンプレート |
㊷賠償責任保険関係書類
| 概要 | 指定訪問介護事業者は、事故が発生した場合に、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため「損害賠償保険に加入しておく」または「損害賠償ができる資産を有している」必要があります。
一般的には損害賠償保険に加入していることがほとんどだと思いますので、保険証書などを事業所で保管しておきましょう。 |
|---|---|
| 基準省令 | (事故発生時の対応) 第三十七条3 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 |
㊸指定関係書類の写し
| 概要 | 訪問介護の開業時に提出した指定申請書と、変更があった場合に提出した変更届出書の控えは、必ず事業所に保管しておきます。
※例えば、以下のような場合には、10日以内に都道府県等へ変更の届出が必要です。
|
|---|
㊹自主点検表
| 概要 | 自主点検表は、指定訪問介護事業者が遵守すべき基準省令や条例、訪問介護費の算定基準について、事業者自身が自ら点検・評価を行うための書類です。
基本的に、指定権者(都道府県や政令指定都市、中核市等の一部の市)ごとに自主点検表を公開していますので、各自治体のホームページを確認して少なくとも年に一度は点検を行いましょう。 ※自主点検表は、大抵の場合、運営指導(実地指導)の事前提出書類に入っています。 |
|---|
必要書類の保管期間について
以下の記録については、サービス完結の日から2年間保存しなければならないとされています。
- 訪問介護計画
- 提供した具体的なサービスの内容等の記録
- 市町村への通知に係る記録
- 苦情の内容等の記録
- 事故の状況および事故に際して採った処置についての記録
※自治体によっては2年ではなく5年としているところが多いため、所管の自治体に確認してください。
記録の保管期間の起算となる「完結の日」は、個々の利用者について、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指します。
※令和3年度の報酬改定で厚生労働省が「完結の日」の明確な解釈を示しました。ただし、従前通りの取り扱いも可能とされており、自治体によって異なる場合がありますので所管の自治体への確認を行ってください。例えば、契約終了日ではなく、「サービス提供した日」や「記録を作成した日」を起算としている地域もあります。
さいごに
今回は訪問介護で揃えるべき書類43種をすべて解説しました。
本記事で紹介した書類があれば問題なく運営できるはずです。かなりの量になりますが何度も読み返し確認してくださいね。
今回紹介した帳票書類のテンプレートを無料でダウンロードできます。
基本的な書類はすべてそろっていますので欲しい方は下記からどうぞ。
また、当サイトではサービス提供責任者の初心者向けマニュアルを無料公開しています。
良ければこちらもチェックしてみてください。